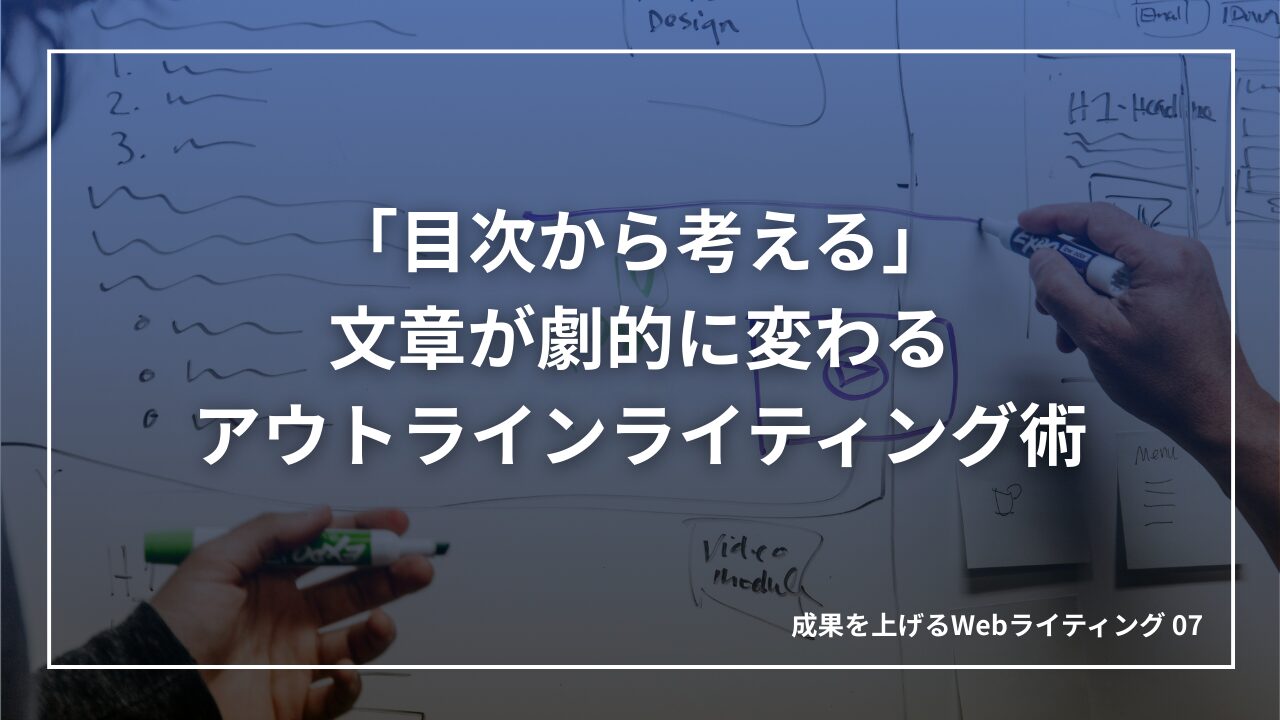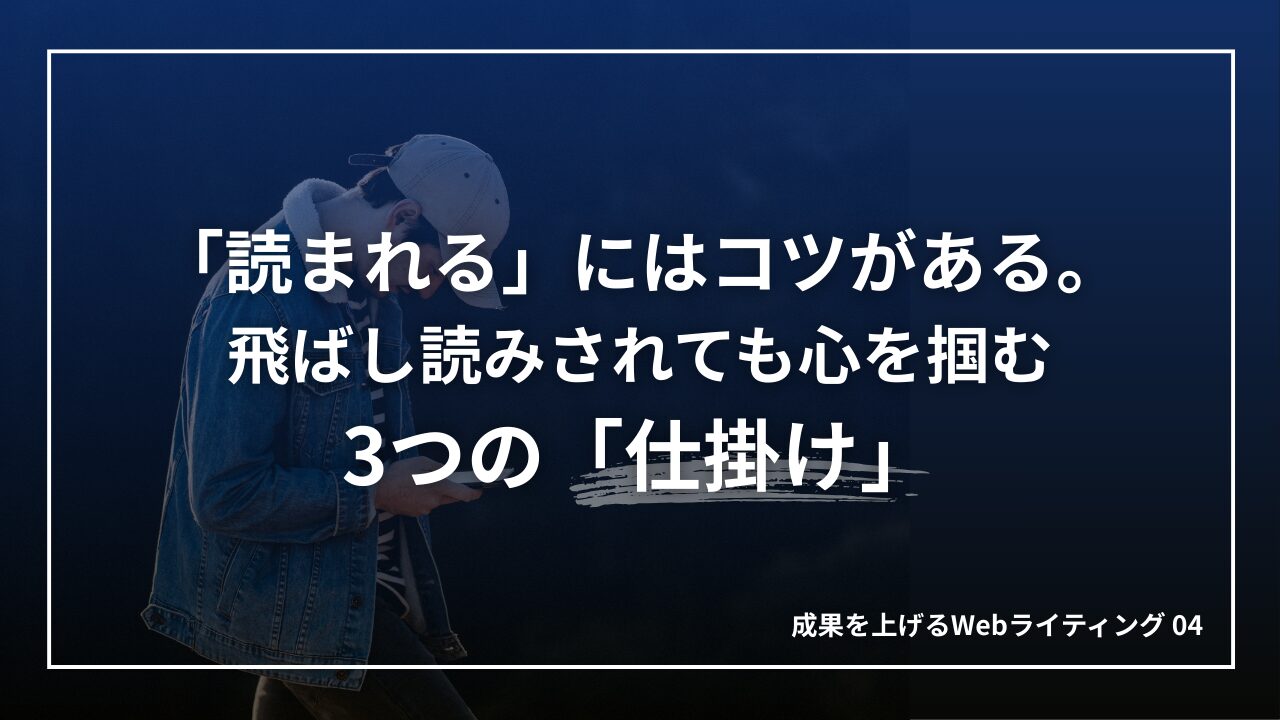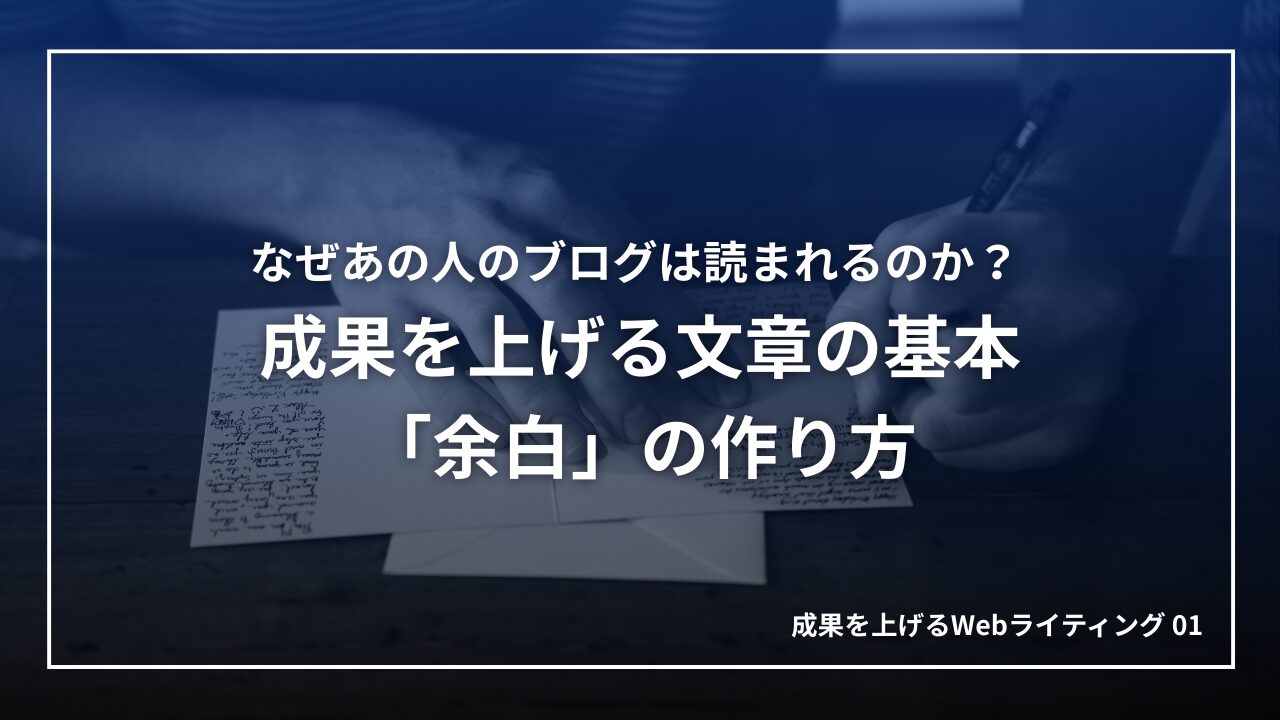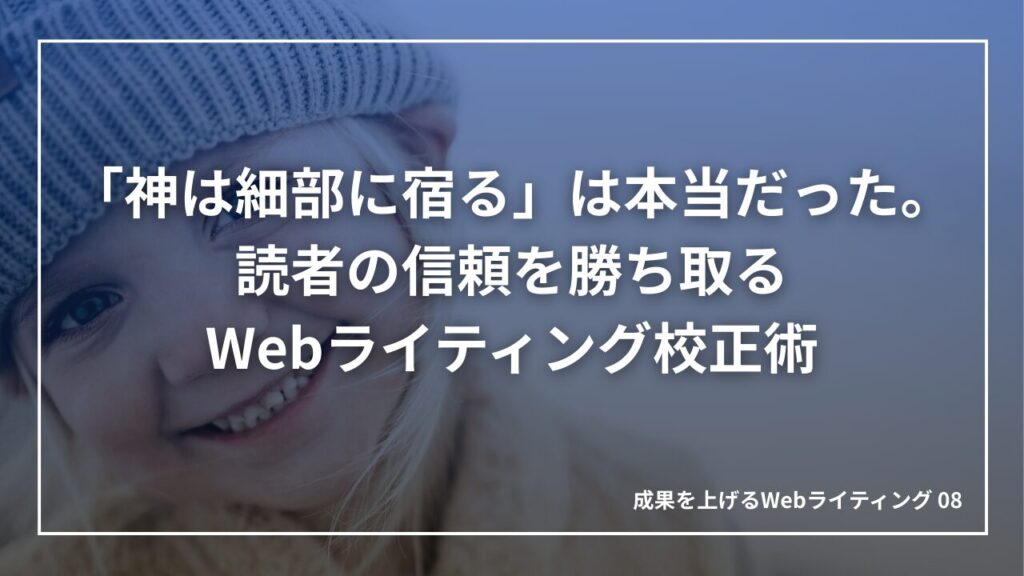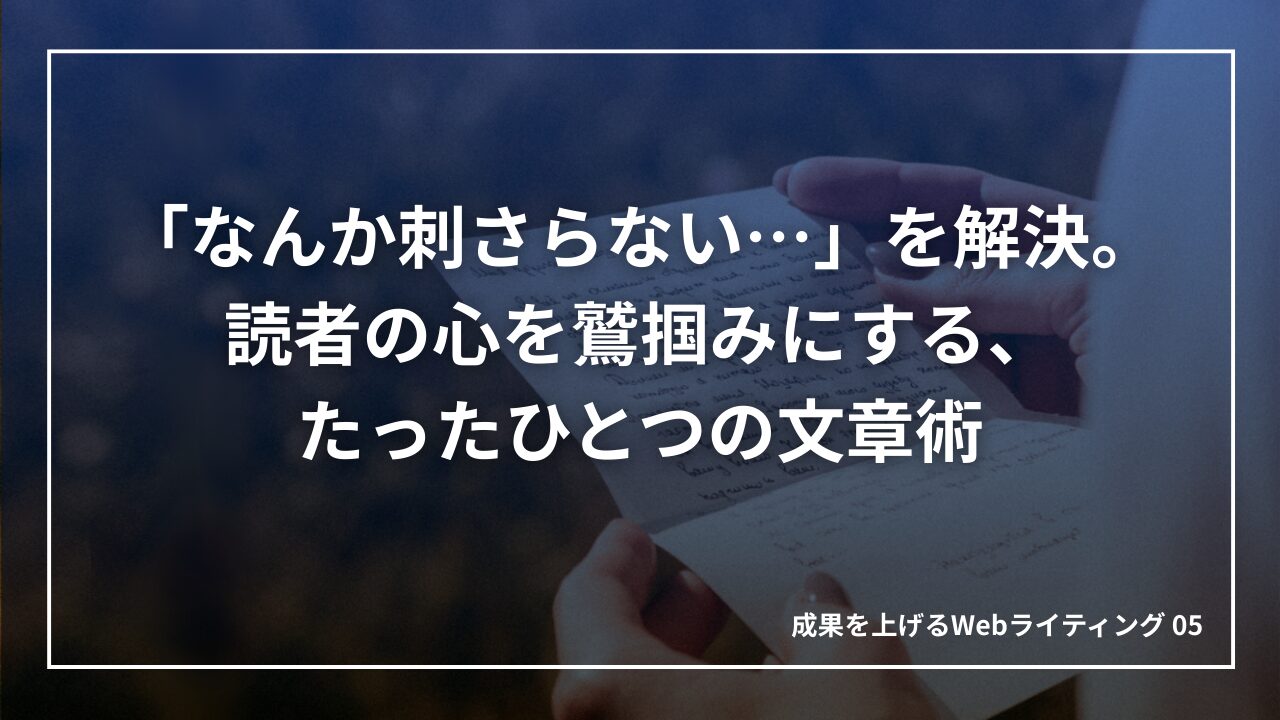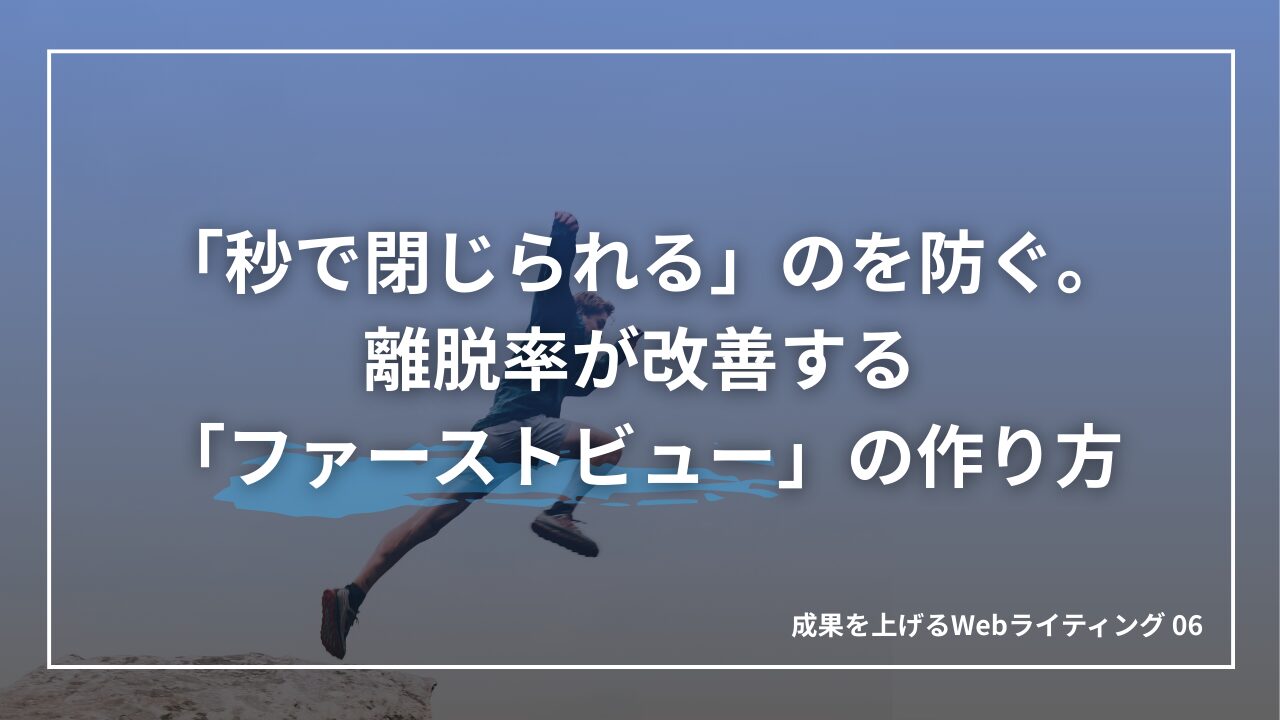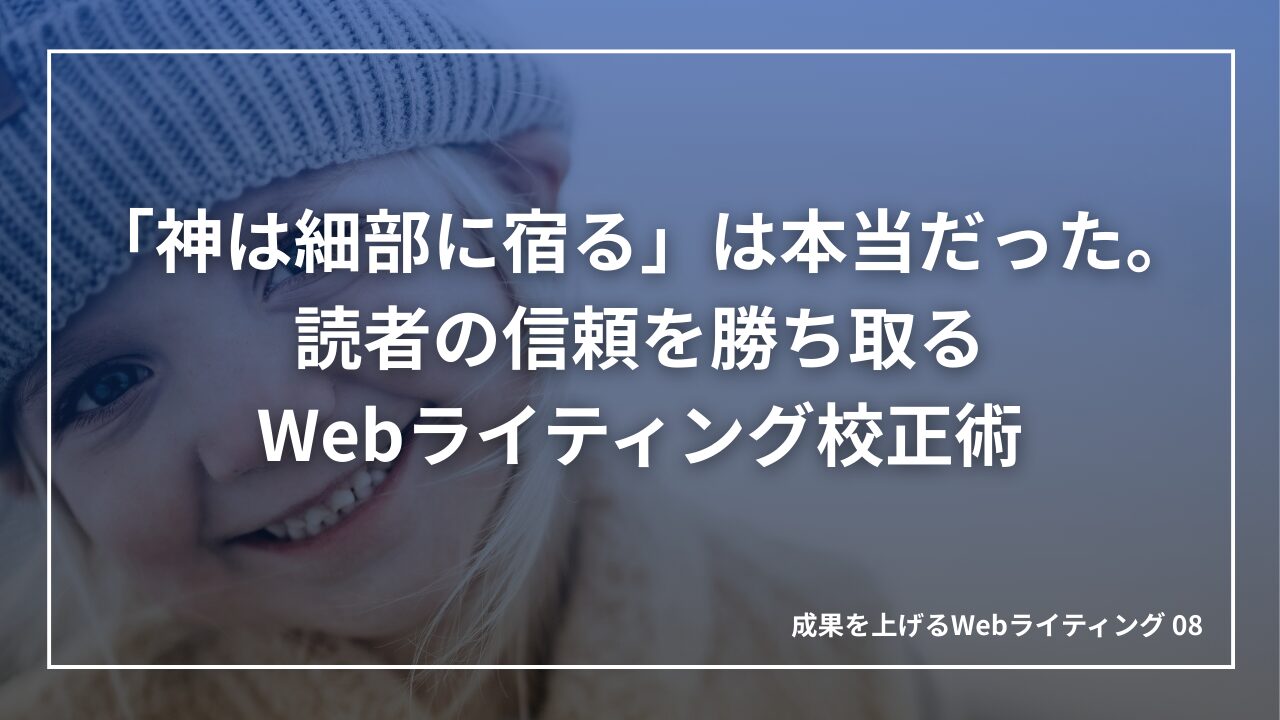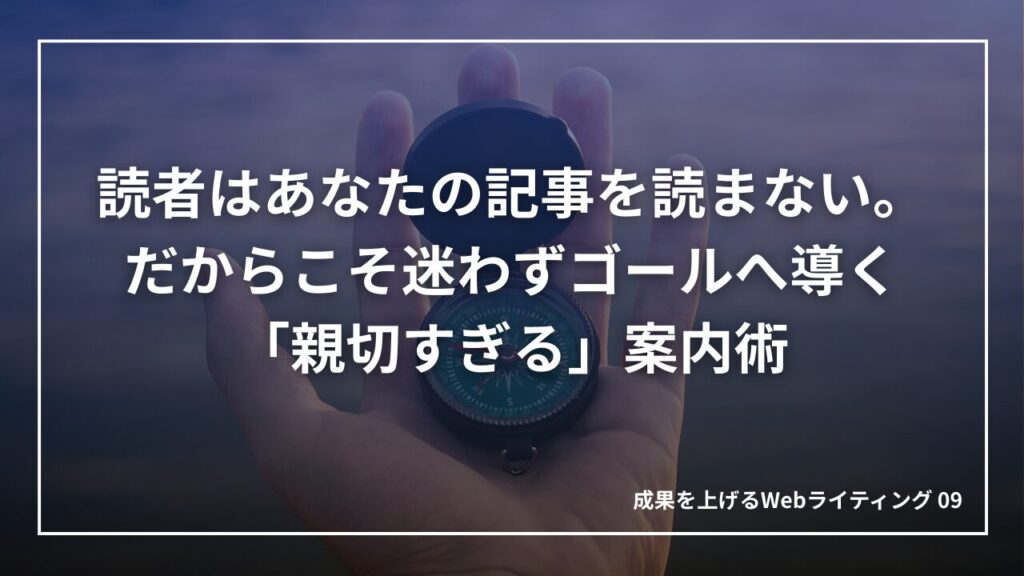
今回は、「成果を上げるWebライティング」のVol.9です。
「この記事、渾身の出来栄えだ!…なのに、なぜか読まれていない…」
ブログを運営していると、そんな壁にぶつかることはありませんか?僕もそうでした。伝えたいことが多すぎて、情報を詰め込みに詰め込んだ結果、出来上がったのは読者を置き去りにする「ただ分かりにくいだけの記事」でした。
ここで正直に告白すると、実は僕、人のブログ記事を上から下まで丁寧に読んだことほとんどありません(笑)。あなたも、そうじゃないですか?
そうなんです!僕は、大きな勘違いをしていたんですね。
それは 「読者は、記事を上から順番に丁寧に読んでくれる」という幻想 です。
読者は、基本的に記事を読みません。正確に言うと「自分が知りたいこと」が書かれている部分だけを探して、つまみ食いするように読むのです。それがネット記事の読み方なんですよね。
では、どうすればいいのか?答えは 「親切すぎるほどの『案内』をすること」 です。ざっくばらんにいえば「誘導」ですかね。読者の知りたそうな部分へいかに上手に誘導できるか?が滞在時間アップや収益化へのポイントなんです。
この記事では、読者を絶対に迷子にさせず、満足度を劇的に向上させるための「案内術」について、僕が培ってきた全てを語り尽くします。
この記事でわかること
- 読者があなたの記事を読んでくれない、本当の理由
- 読者を満足させる「道しるべ」となる具体的なテクニック
- 明日から使える、親切な案内術を盛り込んだ記事構成
なぜ「案内」が重要なのか?読者の残酷な行動心理
ブログ記事って、小説ではなく「辞書」や「マニュアル」に近い存在なんですよね。
読者は、美しい文章表現を味わいに来たのではありません(もちろん、それに越したことはないですが!)。自分の「知りたい」「解決したい」という目的を達成するために、あなたの記事を「使いに」来ているんです。「最短時間で、自分の悩みを解決したい」と思っています。
だから記事にたどり着いた瞬間、無意識のうちにこう考えているんです。
「この記事は、私の悩みを解決してくれそうか?」
「答えは、どこに書かれているんだ?」
この問いに、記事が数秒以内に応えられなければ、読者は容赦なくブラウザの「戻る」ボタンを押します。これが「直帰」です。僕も昔、この直帰率の高さにどれだけ頭を悩ませたことか…。
この大前提に立つと、僕らがやるべきことは一つ。読者が目的の情報をいかに早く、ストレスなく見つけられるか。そのための「案内」を徹底的に整備することです。
読者は、書き手が思っている以上にせっかちで、ワガママです。だからこそ、僕たち書き手は、優秀なツアーコンダクターのように、読者の手を取り、目的地までエスコートしてあげる義務があるんです。そのエスコート術こそが「案内」なんですよ。
【案内術1】目次:記事全体の「地図」を最初に手渡す優しさ
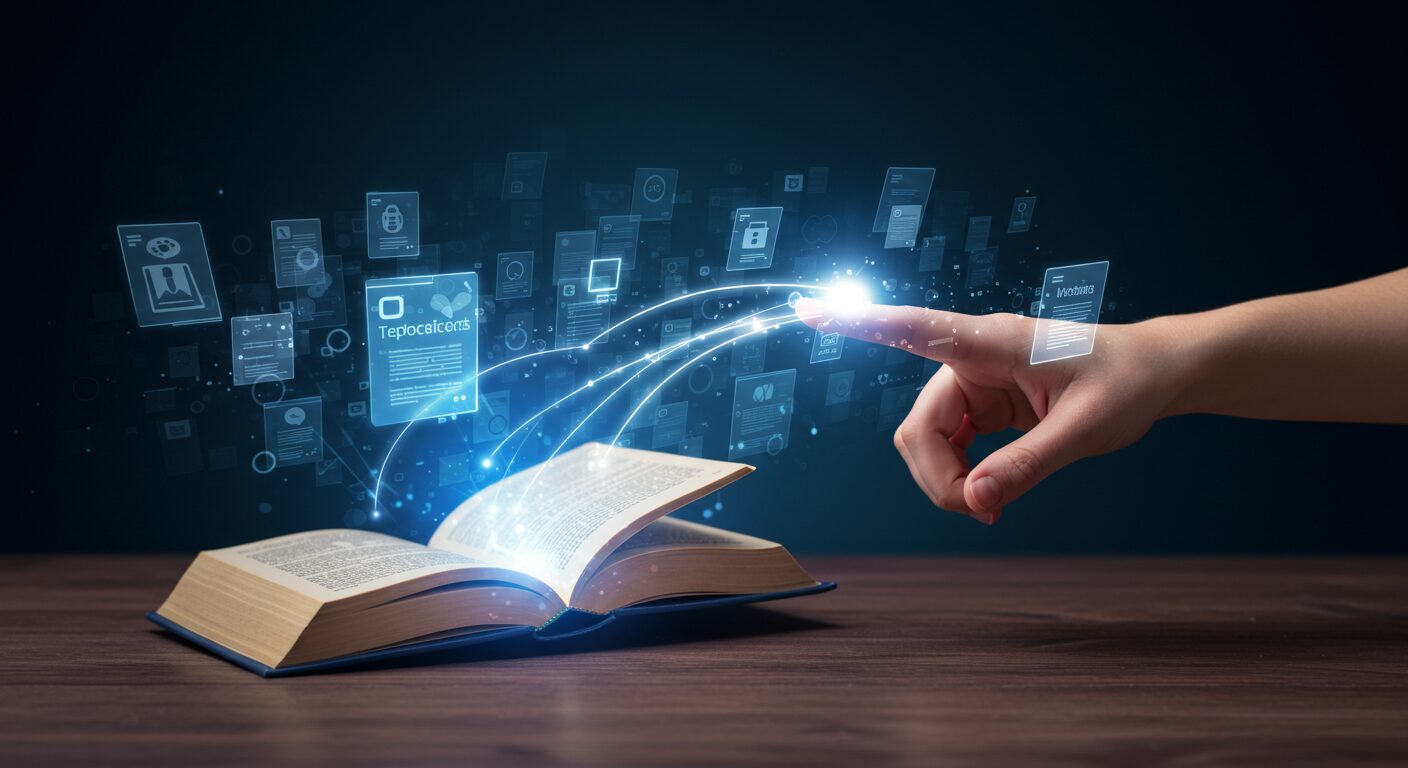
まず、絶対に欠かせないのが「目次」です。
「え、そんな基本的なこと?」と思うかもしれません。ですが、この基本的なことができていないブログが驚くほど多いと感じます。目次のない記事は、入り口にフロアマップのない巨大デパートのようなものです。お目当ての売り場になかなかたどり着けないお客さんは……?どうするか?これじゃ収益化も遠のいてしまいますよね。
目次を設置するメリットは計り知れません。
- 全体像の把握: 読者は記事を読む前に「何が書かれているか」を一覧でき、安心して読み進められます。
- 時間短縮: 自分の知りたい情報が書かれたセクションに、ワンクリックでジャンプできます。これは忙しい読者にとって最高の「おもてなし」です。
- SEO効果: Googleの検索結果に、目次の項目が表示されることがあり(リッチリザルト)、クリック率の向上も期待できます。
目次を作る際は、見出しの言葉をそのまま使うのが基本です。そして、その見出し自体が「読者の興味を引く言葉」になっていることが、次のステップとして重要になります。
「書きたいのに書けない…」その悩み、もくじ(構成)で解決できます。本記事では、執筆スピードと質を劇的に上げる「もくじファースト」思考法を徹底解説。もう文章で迷子にならない、論理的な記事構成の作り方がわかります。
【案内術2】見出し:流し読みでも伝わる「心のフック」を仕掛ける

読者の多くは、本文を読む前に、まず見出しだけをザーッと拾い読みします。この行動を理解すれば、見出しの重要性が見えてきますよね。見出しは、単なる章の区切りではありません。読者の足を止め、本文を読ませるための「強力なフック」なんです。
- 悪い例:
## メリットとデメリット- 良い例:
## なぜ僕が他のサービスではなく、これを使い続けるのか?3つの理由
悪い例は、あまりに無機質でありがちな文言です。これだと何も心が動きません。一方で良い例は、「3つの理由って何だろう?」と、読者の知的好奇心をくすぐります。このように、見出し自体に問いかけや結論、具体的な数字を入れる ことで、読者は「ちょっとここ読んでみよう」という気持ちになるんです。
僕が意識しているのは、「見出しだけを読んでも、記事の8割の内容が理解できるように作る」 こと。これを実践するだけで、流し読みする読者の満足度も格段に上がりますよ。
全部読んだら答えが書いてあるよ的な構造じゃなくて、最初から目次と見出しで読者の知りたい部分へ誘導しちゃうのが、読者の満足度を上げ、結果的に「このブログは分かりやすいな」という信頼につながります。すると滞在時間も伸びて、収益化への道も近づくんですよね。
【案内術3】内部リンク:記事の価値を倍増させる「知識の架け橋」

記事を書いていると、「この用語、前に別の記事で詳しく解説したな」「この話、あの記事の内容と繋がるな」という瞬間が必ずあります。その瞬間こそ、内部リンクを設置する絶好のチャンスです。
内部リンクは、読者を別のページに誘導するだけのものだと思っていませんか?いやぁ、それは本当にもったいない!検索エンジン対策にも非常に有効なんですよ。
例えば、この記事で「SEO」という言葉が出てきたとします。
SEO初心者の読者は「SEOって何?」と疑問に思うかもしれません。
その時、「SEO」と自然に案内してあげることで、読者はストレスなく知識を補完できます。
これは、読者の疑問をその場で解決する「親切心」であると同時に、あなたのブログ内を回遊してもらうための強力な施策でもあります。読者はより深くあなたのブログの世界に没入し、結果として滞在時間も増え、Googleからの評価も高まる。まさに一石三鳥のテクニックなんです。これも「このブログは分かりやすいな」という信頼につながります。
【案内術4】装飾:視覚で誘導する「読みやすさ」の魔法
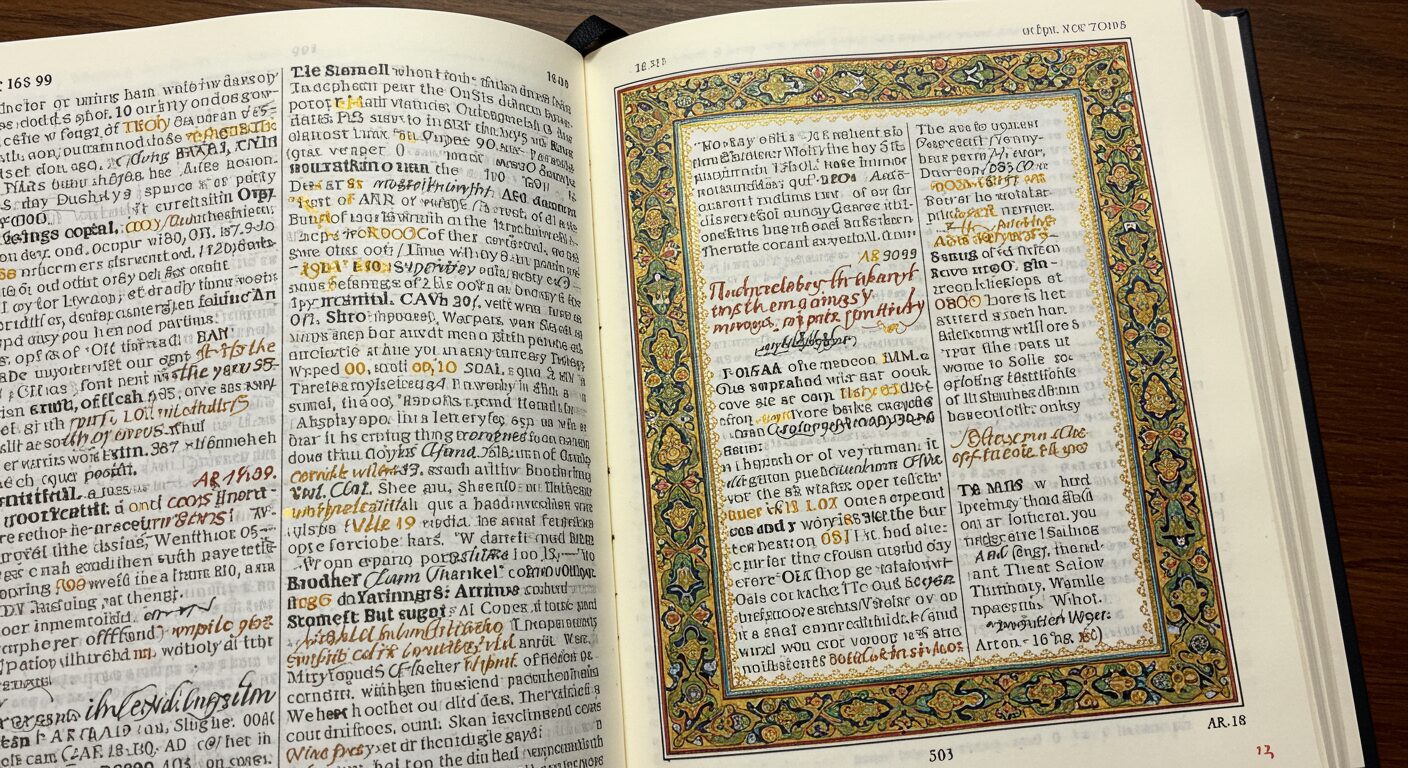
どれだけ良いことを書いても、文字がぎっしり詰まった文章の塊は、それだけで読者に「うわ、読むの大変そう…」という印象を与えてしまいます。
そこで活躍するのが、太字、箇条書き、引用、ボックス(囲み枠) といった装飾です。
- 太字: 「結論から言うと、これが一番重要です」のように、本当に伝えたいメッセージを目立たせる。
- 箇条書き: 3つ以上のポイントや手順を説明する際に使い、情報を整理して見せる。
- 引用・ボックス: 専門家の言葉や、特に重要な補足情報、読者に語りかけるような一言などを際立たせる。
これらの装飾は、ただの飾りではありません。文章に視覚的なリズムを生み出し、流し読みしている読者の視線を強制的に止める効果があります。どこが重要で、どこを読み飛ばしてもいいのかを、書き手側から親切に教えてあげる。これも立派な「案内」の一つですよね。
Webライティングの鍵は「読まれない前提」で書くこと。文字だらけのページを避け、視覚的な工夫で読者の興味を引く方法を、具体例とともに分かりやすく解説します。
「文章が読みにくい…」と悩んでいませんか?本記事では、誰でも簡単に実践できる「余白」の作り方を紹介。これだけであなたの文章は劇的に読みやすくなり、読者の滞在時間もアップします。
まとめ:最高の案内術とは、読者への「徹底的な思いやり」である
ここまで、読者を迷子にさせないための具体的な「案内術」について解説してきました。
- 目次 で、記事全体の地図を渡す。
- 見出し で、流し読みでも内容が伝わるようにする。
- 内部リンク で、知識の橋を架けてあげる。
- 装飾 で、視覚的に読みやすさを演出する。
これらのテクニックは、すべて一つの想いに集約されます。それは、「読者への徹底的な思いやり」 です。
自分の書きたいことを、書きたいように書くのは自己満足でしかありません。読者が何に悩み、何を知りたがっているのか。どうすれば、その答えに最も快適にたどり着けるのか。その一点を突き詰めて考えることこそが、成果を上げるライティング の神髄だと、僕は信じています。
あなたのブログを、日本一親切なテーマパークにするつもりで。ぜひ、今日から「案内術」を実践してみてください。読者の反応が、きっと変わるはずですから。
X(旧Twitter)に投稿した【成果を上げる文章術】シリーズを記事化
書籍おすすめ
読者は、基本的に記事を読みません。「自分が知りたいこと」が書かれている部分だけを探して読む。それがネット記事の読み方なんですよね。
僕ら書き手は、その事実を受け入れた上で、いかに読者を「うまく案内できるか」を考えるべきなんです。親切な案内が設計された記事は、読者の満足度を上げ、結果的に「このブログは分かりやすいな」という信頼につながります。
今回は、こうした文書構造を学習できる書籍を紹介します。僕は全部読みましたが本当にWebライティングに強くなりますよ。
『沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—』(松尾茂起 著)
人気の定番。読者目線での構成や見出し・目次の役割、Web記事の案内力について豊富に解説。実践例も多く、体系的に学びたい人へ。
『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』(唐木元 著)
読者が「知りたい」を見つけやすくするための情報整理、目次や見出しの明確化を徹底解説。迷わない記事構成の実践法も。
『SEOに強い Webライティング 売れる書き方の成功法則64』(ふくだ たみこ 著)
実務での再現性を高めるため、章ごとにチェック項目が細かく提示されているのが本書最大のメリット。SEO初心者が基礎から学ぶ入口にも、経験者が成約率をもう一段引き上げるためのリファレンスにも使える一冊と言える。目次や見出しの最適化による集客・成約力アップ、効率的な記事設計まで、具体例と共に体系的に学べます。
『SEO対策のためのWebライティング実践講座』(鈴木 良治 著)
『SEO対策のためのWebライティング実践講座』は、Googleアルゴリズムが“質”を重視する現代に合わせて、良質コンテンツを作り検索エンジンに正しく評価させる方法を、感覚に頼らない76のテクニックとして体系化した実践書です。キーワード選定から構成・校正・キャッチコピー作成、さらにアクセス解析や無料ツールまで、成果に直結する全工程を1冊で学べます。
補足アドバイス
- 目次は「読者の地図」。冒頭に設置するだけで離脱率低下や満足度UP、SEOへの好影響も期待できます。
- 見出しは「道しるべ」。具体性・情報性・結論を盛り込んで、スクロールで見つけやすい工夫を。
- 500文字に1つ程度の小見出しや、h2/h3タグの階層も意識すると読者にやさしい記事になります。
- 迷わずゴールへ導く“親切な案内人”となるために、上記の書籍・ツールをぜひ活用してみてください!
この記事は X(旧Twitter) で投稿した【成果を上げる文章術】を記事にしたものです。
【成果を上げる文章術 09】
『案内』ブログは縦スクロールして読むメディアですが、上から順番に読んでくれるとは限りません。
ほとんどのユーザーは知りたい箇所だけ探して読みます。
そのため、ユーザーにとって必要な情報に素早く辿り着けるような工夫が必要です。
目次や見出しが有効です。
— ゆきと@コンテンツクリエイター (@tele_commuter) February 1, 2024
このブログではテレワークやパソコンを使って自宅で仕事をするために役立つ小ネタを多数紹介しています。Twitterでも情報発信していますので、今回の記事が役立ったよ!と思ったらTwitterでいいね&フォローお願いします!
Twitter: @tele_commuter