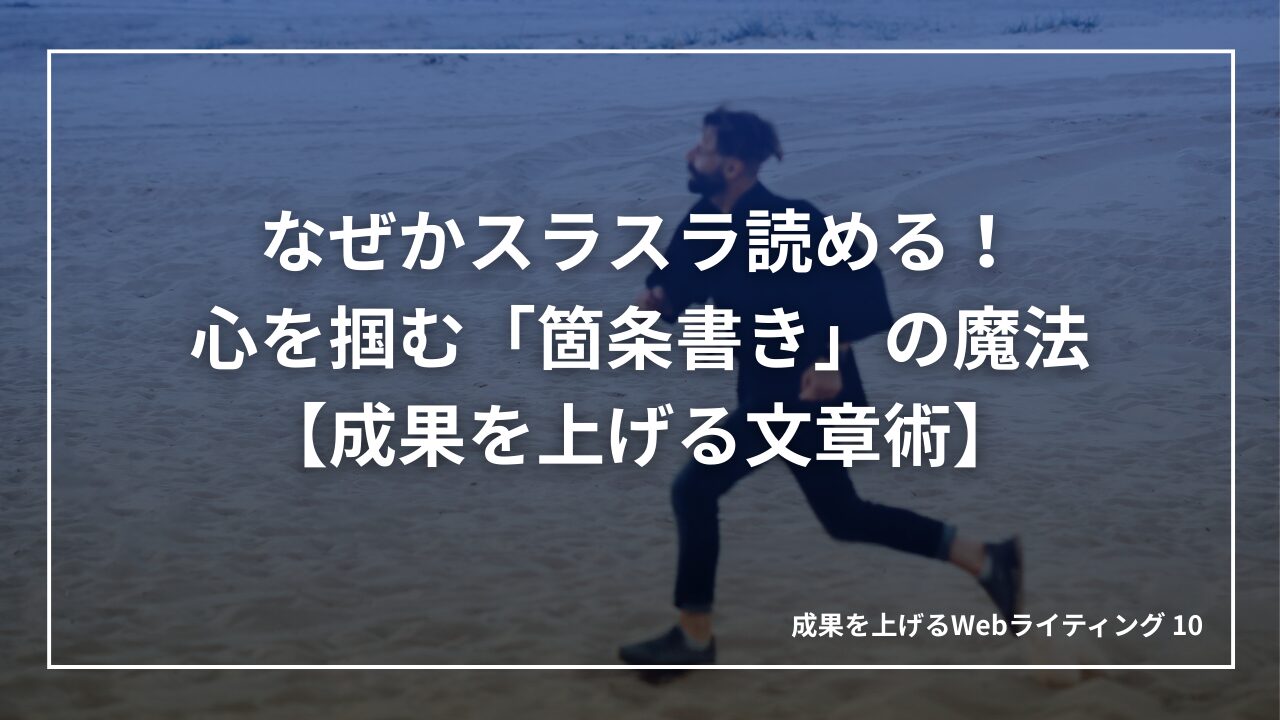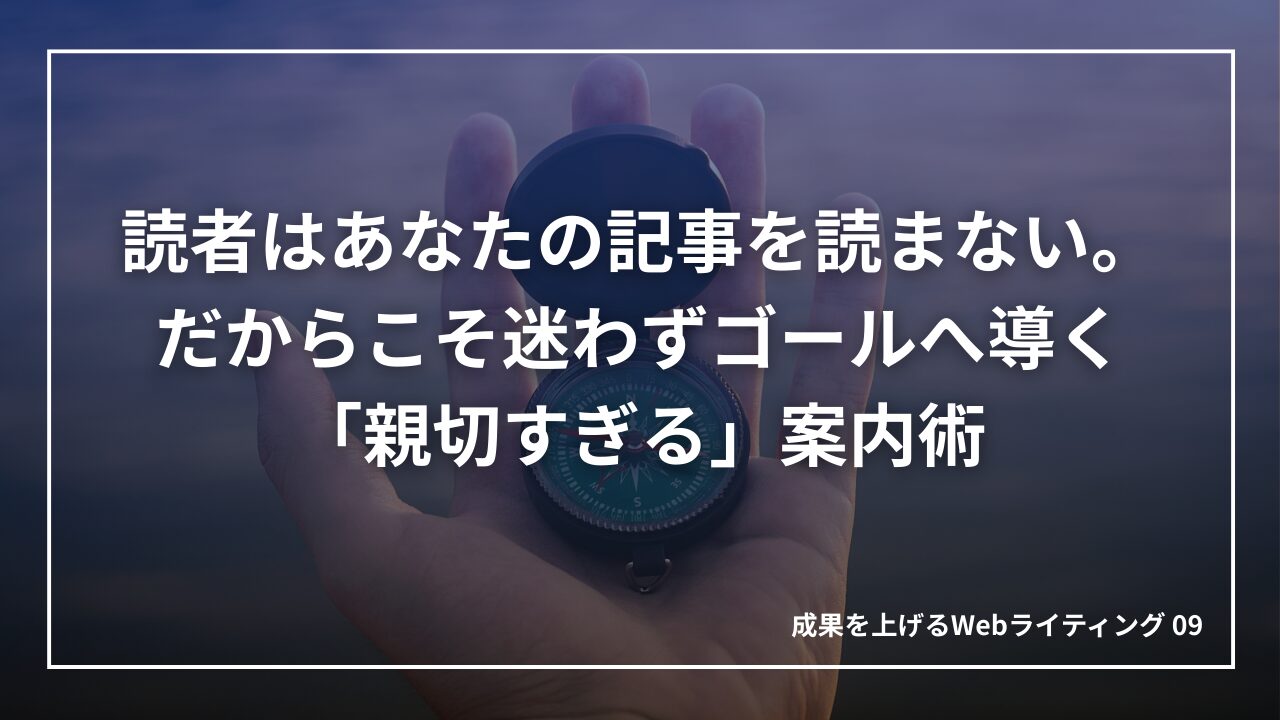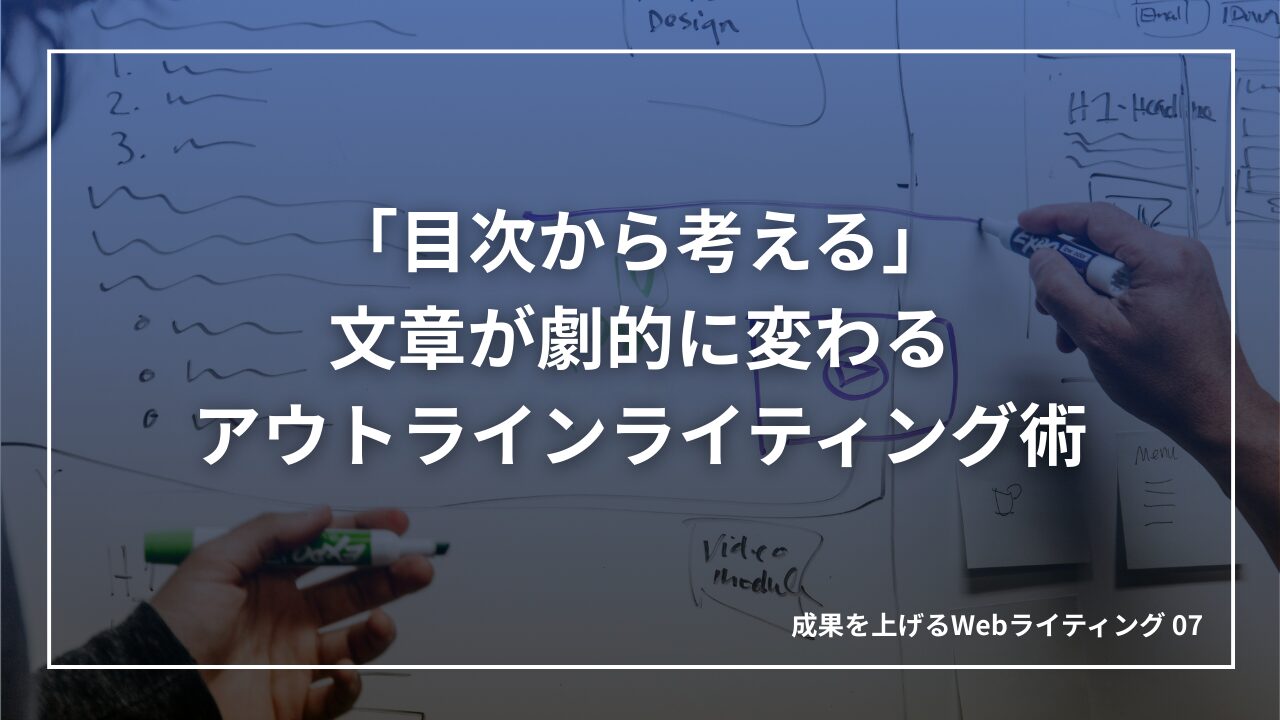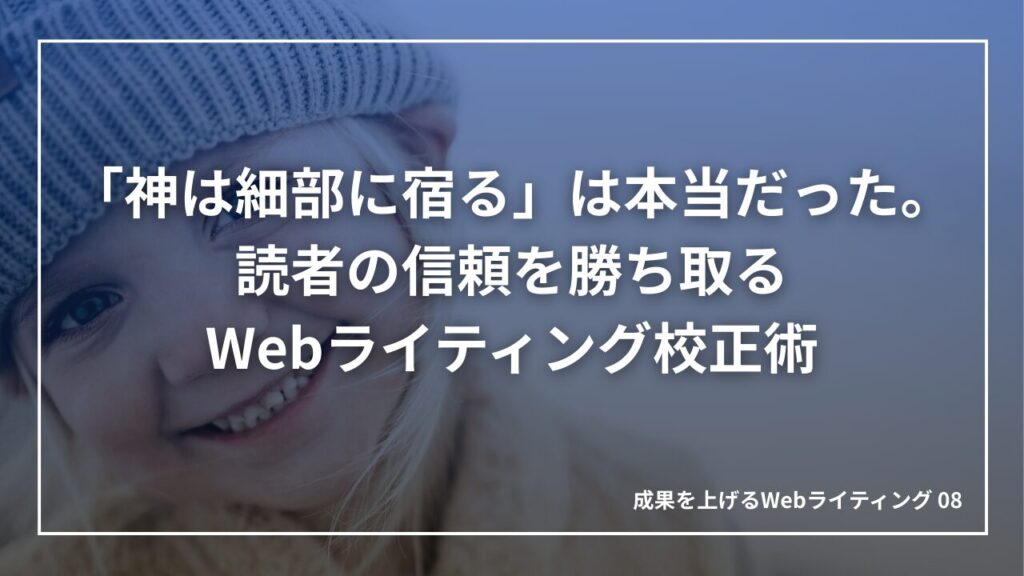
今回は、「成果を上げるWebライティング」のVol.8です。
「よし、完璧な記事が書けた!」
深夜テンションで書き上げた渾身の記事。何度も読み返し、誤字なんて一つもないはず。そう確信して公開ボタンを押した翌朝、何気なく自分の記事を読み返してみると…。
「てにをは」がおかしい…。
なんだこの読みにくい一文は…。
うわ、こんなところに恥ずかしい誤字が…!
そんな経験、あなたにもありませんか?
僕自身がまさにこれでした。書いている最中は、アドレナリンが出ているのか、自分の文章のミスに全く気づけないんですよね。そして、後から見つけては一人で赤面する、という繰り返し。公開ボタンを押すのが怖くなる。。。
「ちゃんとチェックしてるはずなのに、なんでミスを見逃しちゃうんだろう?」
その答えは、校正が単なる「間違い探し」ではない、もっと奥深い作業だからです。
結論から言うと、Webライティングにおける校正とは、**読者への「おもてなし」であり、あなたの信頼性を担保する最後の砦** なんです。
この記事では、僕が数々の恥ずかしい失敗から学んだ「うっかりミス」を防ぎ、文章のクオリティを劇的に上げる「校正」の技術についてお話しします。単なる誤字脱字チェックで終わらない、読者の心を掴んで離さないための「伝わる校正術」について、僕が実践している具体的なテクニックを余すところなくお伝えします。
この記事でわかること
- なぜ自分の文章のミスには気づきにくいのか、その意外な理由
- 文章の品質が劇的に向上する、プロレベルの校正テクニック5選
- コピペで使える!見落としがちなミスを防ぐための「校正チェックリスト」
- 校正は面倒な作業じゃない、あなたの文章への「愛情表現」である理由
なぜ、自分のミスにはこれほど気づけないのか?
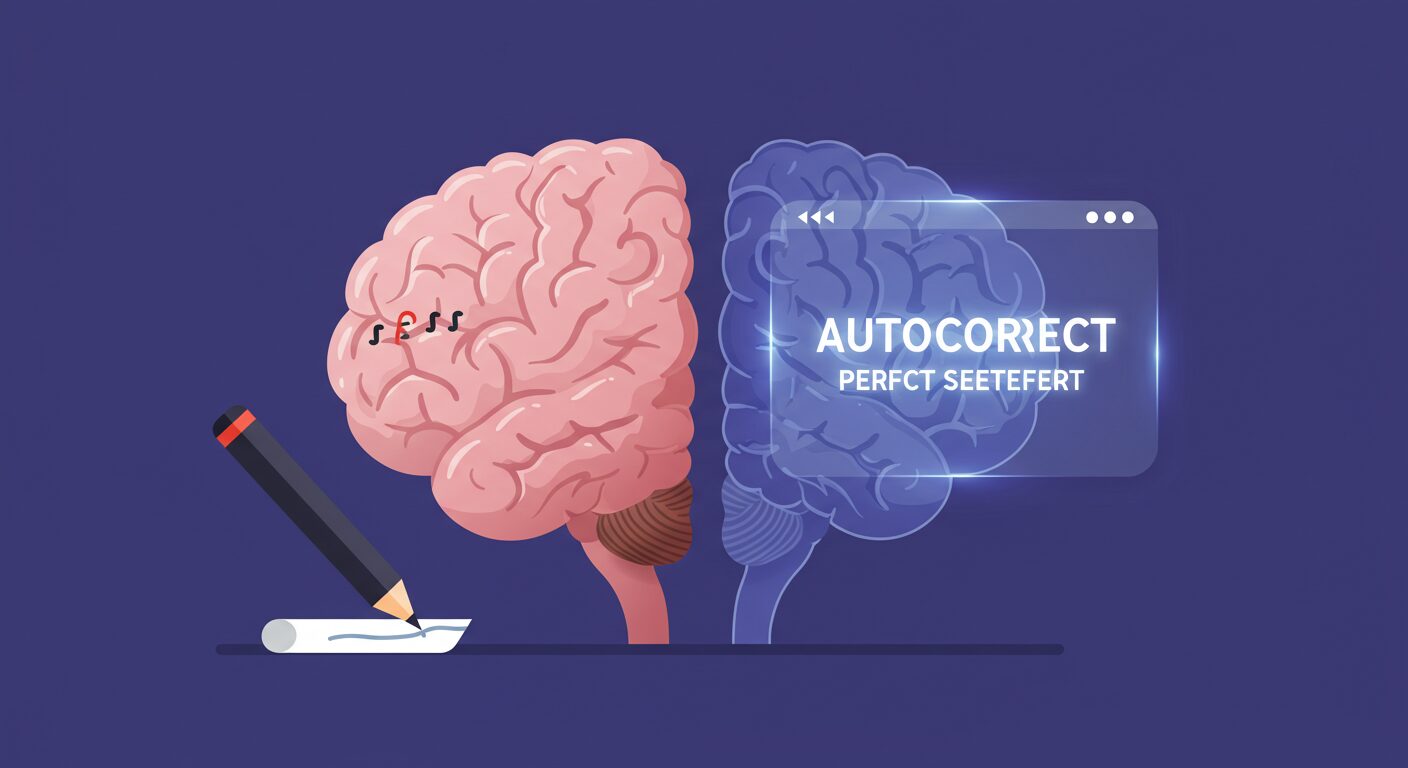
そもそも、どうして僕たちは自分の書いた文章のミスを見つけるのがこんなにも苦手なんでしょうか。それは、決して注意力が散漫だからというわけではないんです。これには、僕たちの「脳の仕組み」が大きく関係しています。
脳の「自動補完機能」という名のワナ
文章を書いているとき、僕たちの頭の中には「伝えたい内容」が明確にあります。脳は、その完成形を知っているがゆえに、文章中の多少のミスやおかしな部分を、**無意識のうちに「正しい文章」として自動で補完して読んでしまう** んですよ。
例えば、「こんちには、世界!」という文章を見ても、一瞬で「こんにちは、世界!」と脳が補正してしまう。これが、書き手本人にだけ働く、強力な「思い込みフィルター」の正体です。
つまり、自分の文章を校正するということは、この脳の自動補完機能という強敵と戦うことでもあるんです。だからこそ、意識的に脳を騙し、文章を「他人の目」で見るための工夫が、めちゃくちゃ重要になってくるわけです。
タイポグリセミア(Typoglycemia)とは、文章中の単語の文字の順番が入れ替わっていても、最初の文字と最後の文字が正しければ、内容を理解できてしまう現象のことです。例えば、「こんちには、みなさん」を「こんにちは、皆さん」と読めてしまうような現象です。
あなたの文章をプロ品質に変える、5つの具体的な校正術

では、どうすれば脳の「思い込みフィルター」を外し、客観的に自分の文章をチェックできるのか。僕が試行錯誤の末にたどり着いた効果絶大の5つの校正テクニックを紹介します。
1.【タイムマシン校正】一晩寝かせて、脳をリセットする
これは基本中の基本ですが、効果は絶大です。書き上げた直後の文章は、自分にとって「我が子」のようなもの。可愛さのあまり、欠点が見えなくなっています。
だから、書き終えたらすぐに公開したい気持ちをグッとこらえて、最低でも数時間、できれば一晩寝かせましょう。
時間を置くことで、書き上げた時の興奮状態がリセットされます。翌朝、フレッシュな頭で自分の文章と向き合うと、まるで他人の書いた文章を読むかのように、冷静な視点を取り戻せるんです。
「うわ、ここの言い回し、くどいな…」
「なんでこんな接続詞を使ってるんだ?」
昨日まで完璧だと思っていた文章の、おかしな点や誤字がやたらと目につきます。時間を置くことで、自分を「読者」の視点に切り替え、客観的に文章をチェックできるようになるんです。まさにタイムマシンですよね。この「違和感」に気づけることこそが、校正の第一歩なんですよ。
2.【五感でチェック】声に出して、耳で聞く
これも最強のテクニックの一つ。黙読ではスラスラ読めているつもりの文章も、声に出して読んでみる と、その印象は一変します。
- リズムの悪い箇所: 何度も噛んでしまったり、息継ぎが苦しくなったりする部分は、一文が長すぎるか、構成が複雑で読みにくい証拠です。
- 論理の飛躍: 「あれ、なんでこの話から次に繋がるんだ?」と、声に出してみて初めて気づく論理の破綻もあります。
- 誤字脱字・てにをはのミス: 目で見るよりも、耳で聞いた方が「音の響き」として違和感をキャッチしやすいです。
目で見るだけでなく「耳で聞く」という別の感覚を使うことで、脳の自動補完を出し抜くんです。ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、効果は絶大ですよ。
僕も、ブログ記事は必ず一度、ブツブツと声に出して読んでいます。周りから見たら少し変な人かもしれませんが、それくらい価値のある作業です。騙されたと思ってやってみてください。文章が驚くほどなめらかになりますよ。
僕の場合ですが、最近は上記の逆パターンで「声でブログ記事を録音して、あとから文字起こしをする」という手順も増えてます。これも別の感覚を使ってチェックできるのでおすすめです。
3.【環境を変える】媒体を変えて、視点を変える
ずっと同じPCの画面で文章を見ていると、目が慣れてしまい、ミスを見逃しやすくなります。そこで有効なのが、文章を表示する「媒体」を変えてみること です。
- 印刷して、紙で読む: デジタル画面とは全く違う視点で文章を捉えられます。赤ペン片手に、紙の上で校正していくと、不思議とミスが見つかりやすくなります。僕も、特に重要な記事は一度印刷してチェックしますね。
- スマホで表示して読む: 今の時代、ブログ読者の大半はスマホユーザーです。PC画面では綺麗に見えていた改行も、スマホで見ると不自然な位置で切れていたり、文字が詰まって見えたりすることがあります。読者と同じ環境でチェックするのは、もはや必須の工程です。
環境を変えるだけで、脳は「いつもと違うもの」として文章を認識し、思い込みフィルターが外れやすくなるんです。
印刷する方法は効果絶大ですがちょっと手間ですよね。紙もったいないし。なので、まずはPCで書いたならスマホで見る、スマホで書いたならPCで見る、という方法を試してみるといいです。
4.【ツールの活用】AIアシスタントを賢く使う
便利なツールを使わない手はありません。最近はAI校正ツールがめちゃくちゃ進化しています。
僕がよく使うのは、文章作成ツールの基本的な校正機能 です。GoogleドキュメントやMicrosoft Wordに標準搭載されている校正機能は、基本的な誤字脱字を見つけるのに非常に便利です。これらは単純な誤字脱字だけでなく、文法的な誤りや、より自然な表現の提案までしてくれます。音声からの文字起こしも優秀です。
また、ChatGPTやGeminiなどのAIアシスタントに校正を依頼するのもいいですね。ただし、ツールを100%過信するのは危険 です。AIは文脈や、あなたが本当に伝えたい微妙なニュアンスまでは汲み取ってくれません。あくまで優秀な「壁打ち相手」あるいは「アシスタント」として活用するのがベスト。
僕の使い方は、まずツールで機械的なミスを徹底的に洗い出し、修正候補を検討する。そして、その後に必ず自分の目と耳(音読)で最終チェックをする、という流れです。監督はあくまであなた自身ですからね。
5.【最終兵器】第三者の目に頼る
もし可能であれば、家族や友人、同僚など、自分以外の誰かに読んでもらう こと。これが最も強力な方法です。
自分では完璧に説明したつもりの箇所が「ここの意味、よく分からないんだけど…」と指摘されたり、思いもよらない誤字を笑われたり(笑)。
他人の目は、自分では絶対に外せない「思い込みフィルター」をいとも簡単に取り払ってくれます。やってみるとわかりますが、「もうやめてくれ!」と言いたくなるほどミスが出てきたりします。超強力な方法です。もし頼める相手がいるなら、ぜひお願いしてみてください。お金を払ってでも、プロの校正者に依頼する価値がある場合もありますよ。
コピペで使える!僕の校正チェックリスト

具体的なテクニックと合わせて、僕が実際に使っているチェックリストを共有します。校正する際に、ぜひ活用してみてください。
【校正チェックリスト】
▼ 誤字脱字・変換ミス
[ ] 誤字、脱字はないか?
[ ] 漢字の変換ミスはないか?(例:「以外」と「意外」、「対象」と「対照」)
[ ] 同じ単語の表記は統一されているか?(例:「Web」と「ウェブ」、「ブログ」と「blog」)▼ 文章の読みやすさ
[ ] 一文が長すぎないか?(60文字程度を目安に)
[ ] 読点(、)は適切に使われているか?
[ ] 主語と述語の関係は明確か?
[ ] 接続詞は効果的に使われているか?(「しかし」「そして」の多用など)▼ 表現・トーン
[ ] 全体を通して文体(ですます調など)は統一されているか?
[ ] 専門用語を使いすぎていないか?読者に伝わる言葉か?
[ ] 事実と意見が混同されていないか?
[ ] 不快感を与えるような断定的な表現はないか?▼ 全体の構成
[ ] 見出しだけで記事の全体像が掴めるか?
[ ] 各セクションで伝えたいことは明確か?
[ ] 話の脱線や、論理の飛躍はないか?
まとめ:校正は、あなたの文章への「最後の愛情表現」

ここまで、僕が実践している校正術について語ってきました。
もしかしたら、「校正って、なんて面倒なんだ…」と感じたかもしれません。確かに、手間も時間もかかります。でも、僕はこう思うんです。
校正とは、自分が生み出した文章への「最後の愛情表現」であり、時間を割いて読んでくれる読者への「最高のおもてなし」である、と。
誤字だらけの文章は、ホコリだらけの部屋に客人を招くようなもの。せっかく素晴らしい情報(家具)が揃っていても、居心地が悪ければすぐに帰ってしまいますよね。
あなたの渾身の記事を、最高の状態で読者に届けるために。そして「この人の記事は、いつも読みやすくて信頼できるな」と思ってもらうために。
地味な作業だけど、校正プロセスって本当に大切ですね。そのひと手間が、自分の文章を、そしてブロガーとしての自分自身を、確実に成長させてくれるはずですから。
書籍おすすめ
文章の校正は、単なる間違い探しではありません。読者に対する「おもてなし」であり、記事の信頼性を担保するための重要な作業です。
書き上げた情熱を、誤字一つで台無しにしてしまうのは、本当にもったいない。そんな校正についてもっと深く理解できる書籍を紹介します。
『校正のレッスン 活字との対話のために』(大西寿男 著)
校正の仕事や実際の現場についてわかりやすく解説。初心者にもやさしい内容で、セルフ校正の感覚や着眼点が身につきます。
『校正のこころ 積極的受け身のすすめ』(大西寿男 著)
長年の経験をもとに、校正する上での心構えや「言葉との向き合い方」まで学べ、より高い文章の質を目指したい方に最適。
『セルフパブリッシングのための校正術』(大西寿男 著)
ブロガーやWebライター、電子書籍ユーザーにもおすすめ。プロ校正者の実践スキルをわかりやすく紹介しています。
 センパイ
センパイ どの本も文章力アップの勉強になります。
この記事は X(旧Twitter) で投稿した【成果を上げる文章術】を記事にしたものです。
【成果を上げる文章術 08】
『校正』伝わりやすい文章か、誤字脱字がないかのチェックのため、文章を書いた後に校正すると良いです。
1、一晩寝かせて再チェックする
2、声に出して読んでみる
など、有効です。文章チェックのできるエディタ(GoogleドキュメントやWORD等)も便利ですよ。
— ゆきと@コンテンツクリエイター (@tele_commuter) January 30, 2024
このブログではテレワークやパソコンを使って自宅で仕事をするために役立つ小ネタを多数紹介しています。Twitterでも情報発信していますので、今回の記事が役立ったよ!と思ったらTwitterでいいね&フォローお願いします!
Twitter: @tele_commuter