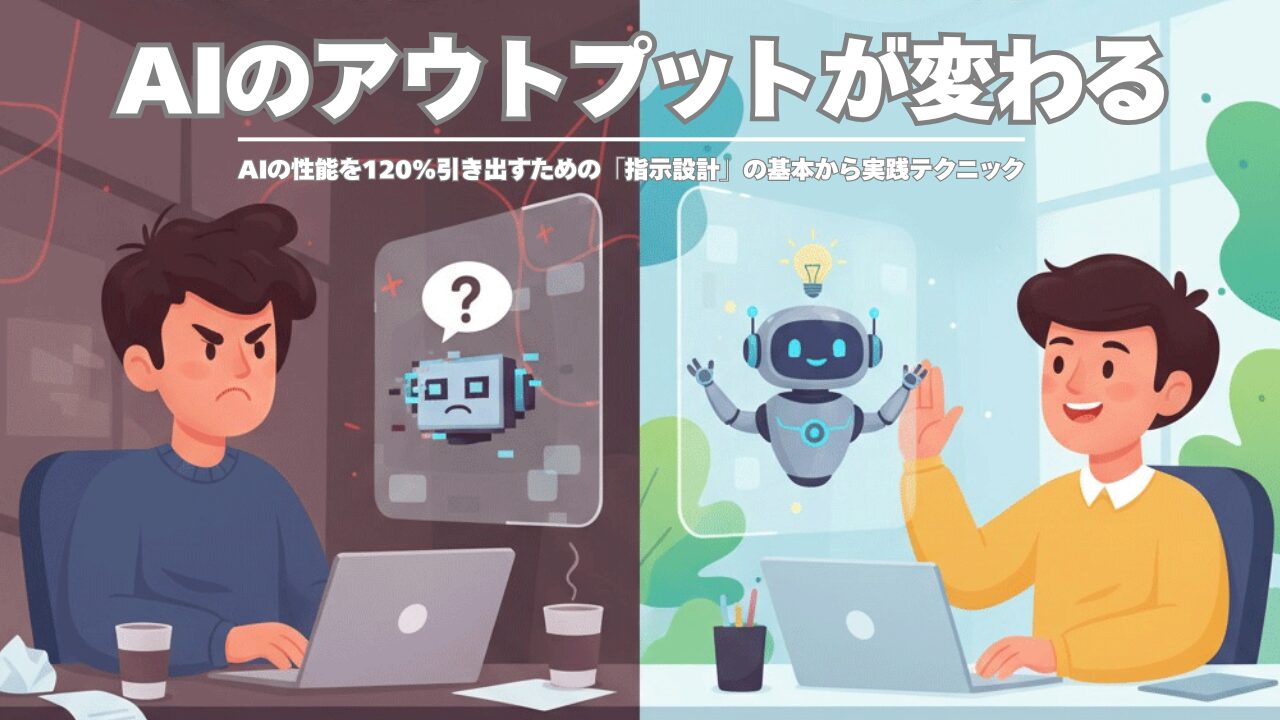「AI って、なんだか難しそう…」
「一部の専門家やクリエイターが使うもので、自分には関係ない世界の話でしょ?」
その気持ち、めちゃくちゃ分かります。僕自身もほんの数年前までそう思っていましたから。
スマートスピーカーが鳴り物入りで登場した時も、すぐに飛びついて買ってみたものの、結局、天気予報を聞くくらいで、すぐにホコリをかぶってしまいました。Siri や Google アシスタントも同じです。目新しさから最初こそ使ってみたものの、まともに会話が成り立たない。「AI って、所詮こんなものか」と、どこか冷めた目で見ていたんです。
でも、もし今、当時の僕と同じように感じているなら…、この記事で伝えたいことがあります。
なぜなら、今の AI をめぐる状況は、10〜20 年前の「あの転換期」にとてもよく似ていると、僕には感じられるからです。
この記事は、かつて AI にまったく期待していなかった僕が、なぜ今「AI は全員が使うべき必須スキルだ」と確信するに至ったのか、その理由と具体的な体験談をお伝えするものです。
この記事を読み終える頃には、AI に対する見方が変わり、「ちょっと触ってみようかな」という気持ちが芽生えてくるかもしれません。
この記事でわかること
- なぜ今、AI が「メールや PC と同じくらい当たり前」のスキルだと言えるのか
- 僕が AI を「おもちゃ」から「最強の相棒」だと認識し直した衝撃の体験
- 価値観が激変した「本物の AI」との出会い
- 初心者でも今日から始められる具体的な AI ツールと活用術
僕が AI を「使えないポンコツ」だと勘違いしていた頃
2010 年代後半、世はまさに「スマートスピーカー戦国時代」。僕も例に漏れず、新しいもの好きとして早速 Amazon Echo や Google Home を家に迎え入れました。「アレクサ、電気つけて」「OK Google, 今日の天気は?」なんて、SF 映画みたいな未来が来たと最初は興奮したものです。
でも、その興奮は長くは続きませんでした。
「今日のオススメの曲をかけて」と頼めば、いつも同じような曲ばかり。「おもしろい話をして」と無茶振りすれば、ネットで調べたような薄いジョークが返ってくる。だんだんと、スマートスピーカーはただの「声で操作できる時計付きスピーカー」になっていきました。
Siri や Google アシスタントも同様でしたね。スマホに向かって話しかけるのが気恥ずかしいのもあって、結局使うのはカップラーメン作る時のタイマーをセットするときくらい。
BMW の車に搭載されている音声アシスタントも、運転中にハンズフリーで操作できるのは便利ですが、こちらの意図を正確に汲み取ってくれることは稀で、「もういいや」と結局自分で操作してしまうことがほとんど。
AI とは、決められた質問に、決められた答えを返すだけのお利口なプログラム。それが、僕の正直な AI に対する評価でした。
しかし、2023 年頃から、その価値観は大きく覆されることになります。
価値観が壊された「本当の生成 AI」との出会い
転換点は、ChatGPT、そして Google の Gemini(当時は Bard) といった「生成 AI」の登場でした。
「ブログ記事のアイデアを 10 個出して」
「この文章を、もっと読者がワクワクするような表現に書き換えて」
「この機能を実現するための Python コードを書いて」
僕が投げかけた曖昧な言葉を、AI は驚くほど的確に理解し、人間が書いたとしか思えない、質の高いアウトプットを次々と生み出してくれる。
「うわー…なんだこれ…」
衝撃でした。今まで僕が「AI」だと思っていたものとは、次元やレベルがまったく違いました。これは「命令に答える」だけのプログラムじゃない。「理解」して「創造」してると。
そこから僕は、Midjourney(画像)や、Suno(音楽)、Claude(文章)、NoteBookLM(辞書)、Perplexity(検索)といった、さまざまな AI にどっぷりとハマっていきました。
気づけば僕は、かつてスマートスピーカーに感じていた「使い道がわからない」という悩みとは無縁になっていました。むしろ、「時間が足りない!もっと AI と遊びたい!もっと作りたい!」という、ポジティブな欲求に満ち溢れていたんです。
そして何よりすごいのが、これらの AI は 「遊んでいるだけで、収益化できるかもしれない生成物が生まれる」 という点です。
ブログ記事の構成案、SNS 投稿の文章、プレゼン資料のデザイン、Web サイトのコード、果ては作曲まで。これらが、専門知識がなくても、アイデアと AI との対話だけで形になっていく。
このすごさ、この興奮を、まだ体験していない人がいるなんてもったいなさすぎる!僕は本気でそう思っています。
15 年前、「インターネットはマニアが使うもの」という時代があった
少し昔話をさせてください。
2000 年代。世の中では急速にインターネットと E メールが普及し始めていました。今では信じられないかもしれませんが、当時はまだパソコンが苦手でメールを使えないという中高年の上司がゴロゴロいたんです。
「おい、すまんが、この手紙をメールでこの人に送っといてくれんか」
手書きのメモを渡され、若手社員が上司になりすましてメールを送る。そんな光景が日常的に繰り広げられていました。
彼らは、新しい技術の登場に戸惑い、変化を拒み、結果として時代の流れから取り残されていきました。
それだけじゃない。昭和を生きてきた僕は、ポケベルという文化が終わって PHS に移り変わる時にも「電話機持って歩いてどうするんだよ。そんなに電話する用事があるのか?お大尽か」とか、PHS からガラケーになる時も、ガラケーからスマホになる時も「携帯電話でネット見てどうするんだ?ウケる~」とか本気で言う人をこの目で数多く見てきました。
「パソコンなんて、一部の詳しい人か仕事で使うものでしょ」
「インターネットはなんだか怖い」
「メール?手紙か電話で十分だよ」
そんな声が、まだ当たり前に聞こえてきた時代でした。今だから違和感を覚えるのかもしれませんが、当時は多くの人にとって、それが当たり前の感覚だったと思います。
では、現代はどうでしょう。パソコンやスマホなしの生活なんて、もはや想像できませんよね。メールや LINE での連絡は当たり前。インターネットで情報を調べ、動画を観て、買い物をするのが日常です。
かつて「一部の人の特別なツール」だったものは、この 15 年で、誰もが使いこなす 「社会のインフラ」へと変わったのです。
僕が今、AI に感じているのは、まさにこの変化の始まりの匂いです。
15 年前、「パソコンなんていらない」と言っていた人が、今どうしているか。おそらく、時流に追いつこうと必死で使い方を覚えたのではないでしょうか?あるいは時代の変化から取り残されてしまったかもしれません。
歴史は繰り返します。15 年後の 2040 年、AI を使いこなすことは、現代の我々がスマホを使いこなすのと同じくらい「当たり前」のスキルになっていると、僕は確信しています。
もう数年もすれば、生まれた時からAIとともに育ってきた子供たちが、ネットで活躍する時代になるはずです。
「AI に仕事を指示する」「AI と一緒にアイデアを練る」「AI に単純作業を任せる」。これが、あらゆる仕事のスタンダードになる。その時、「AI は難しそうだから」と避けてきた人は、一体どうなってしまうのか。そう考えると、少し怖くなりませんか?
でも、大丈夫。今なら、まだ全然間に合います。なぜなら、この革命はまだ始まったばかりなのですから。
AI は「仕事を奪う」のではなく「仕事のやり方を変える」インフラである
「AI に仕事が奪われる」
そんなディストピアな未来を語る声もよく耳にします。確かにそうした不安はあるでしょう。でも、僕は全く逆のことを感じています。
AI は、僕たちの仕事を奪う敵ではありません。それは、電気や水道、インターネットと同じ 「社会インフラ」です。
インターネットが登場した時、「電話交換手の仕事がなくなる!」と叫ばれました。しかし実際には、E コマース、SNS マーケター、Web デザイナーといった、それまで存在しなかった新しい仕事が爆発的に生まれ、社会はより豊かになりました。
AI も全く同じなんじゃないかと思うんです。AI の登場によって縮小してしまう職種もあるかもしれません。しかし、それ以上に、AI を「使いこなす」ことで生まれる新しい価値や、新しい職業が、これからどんどん増えていくはずです。
事実わかりやすいところでいえば、AI に指示を与える「プロンプトエンジニア」という職業も出始めていて、年収 1,000 万クラスに届く人もいると聞きます。
好き嫌いに関わらず、僕たちは AI というインフラの上で生きていくことになる。だとしたら、僕たちが考えるべきは一つだけ。
「この新しいインフラを、どうすれば自分の仕事や生活を豊かにするために使いこなせるか?」
この視点を持つことこそが、AI 時代を生き抜くために必要になってくるのかもしれません。
もちろん、AI の学習データに使われる著作権や、クリエイターの方々の権利については、現在も非常に重要で活発な議論がなされていると認識しています。そうした問題が早急に解決されて、誰もが気持ちよく AI を扱える日がくればいいと思います。
難しくない!怖くない!今日から始める AI とのお付き合い
「でも、やっぱり何から始めたらいいか…」
そうですよね。その気持ち、痛いほどわかります。だからこそ、僕が実際に使ってみて「これは!」と思った、初心者でも安心して始められる AI ツールをいくつかご紹介します。
大事なのは、「勉強する」と意気込むのではなく、「まず遊んでみる」ことです。
| AI ツール名 | 種別 | こんな人におすすめ&最初のステップ |
|---|---|---|
| ChatGPT | 文章生成 AI | 文章を書くのが苦手な人、アイデア出しに詰まりがちな人。 まずは「自己紹介の文章を考えて」「今日の夕飯の献立を 3 パターン提案して」など、身近なことから話しかけてみましょう。 |
| Gemini | 文章生成 AI | Google のサービスをよく使う人、正確な情報が欲しい人。 「〇〇(最新のニュース)について、小学生にもわかるように要約して」と頼んでみてください。その精度の高さに驚くはずです。 |
| ImageFX | 画像生成 AI | 絵心はないけど、面白い画像を作ってみたい人。 「空飛ぶラーメン」「寿司に乗る宇宙飛行士」など、思いつくままのキーワードを入力して、AI のユニークな発想を楽しんでみてください。 |
| Perplexity AI | AI 検索エンジン | 知りたいことを効率的に調べたい人。 従来の検索のようにキーワードを並べるのではなく、「〇〇と △△ の違いを、メリット・デメリットの表で教えて」と、会話するように質問するのがコツです。 |
どうでしょう?どれも、まるでゲームみたいに始められそうだと思いませんか?
僕は「この言い回しどうもしっくりこない。もっと良い言い回しある?」とよく聞いています。これが毎回良いアドバイスが返ってくるんですよね。
最初は、AI が期待通りの答えを返してくれないこともあるでしょう。でも、それこそが AI と付き合う上での醍醐味なんです。「どう言えば、もっとうまく伝わるかな?」と試行錯誤するプロセスは、まるで新しい友達と仲良くなる過程のようです。
この「AI との対話能力」こそが、これからの時代を生き抜く上で、間違いなくあなたの強力な武器になります。
そして、そのうちに自分のお気に入りの AI が見つかると思います。
まとめ:15 年後、笑われる側にならないために
「ググる」
Google で検索するという意味のネットスラングですが、今後は、「チャトる(ChatGPT に聞く、の意)」や「パプる(Perplexity)」なんて言葉が標準化してくるかもしれません。いや、実はすでに AI 界隈では当たり前に使われている言葉です。
もう、そういう世界が始まってきているんです。
今、AI を使いこなせるかどうかは、まだ個人のスキルや興味の差でしかありません。実際、すでに当たり前に生活や仕事の中で AI を使いこなしている人も多いですが、まだまだ AI に触ったことがないという人もとても多いです。
しかしこれから先、AI を使うことが「当たり前」になった時、その差は「できる人」と「できない人」を分ける、決定的な断絶になります。
かつて僕たちが「メールの打ち方を知らない上司」を見て感じた、あの何とも言えない感情を、未来の若者たちから向けられる側になってはいけません。
AI を難しく考える必要はありません。まずは ChatGPT に「面白い冗談を言って」と話しかける、その小さな一歩からでいいと思います。今 AI を使いこなしている人だって、最初は恐る恐るそんな質問を投げかけることから始まったんです。
この小さな一歩が、15 年後のあなたを支える、大きな資産になるはずです。
最初は怖いかもしれない。でも安心してください。AI は、あなたが思っているよりもずっと優しく、そして驚くほど優秀なパートナーになってくれるはずです。
—–
ほかにも「AI」関連の記事を書いています。ぜひ読んでみてください。
このブログではテレワークやパソコンを使って自宅で仕事をするために役立つ小ネタを多数紹介しています。Twitterでも情報発信していますので、今回の記事が役立ったよ!と思ったらTwitterでいいね&フォローお願いします!
Twitter: @tele_commuter