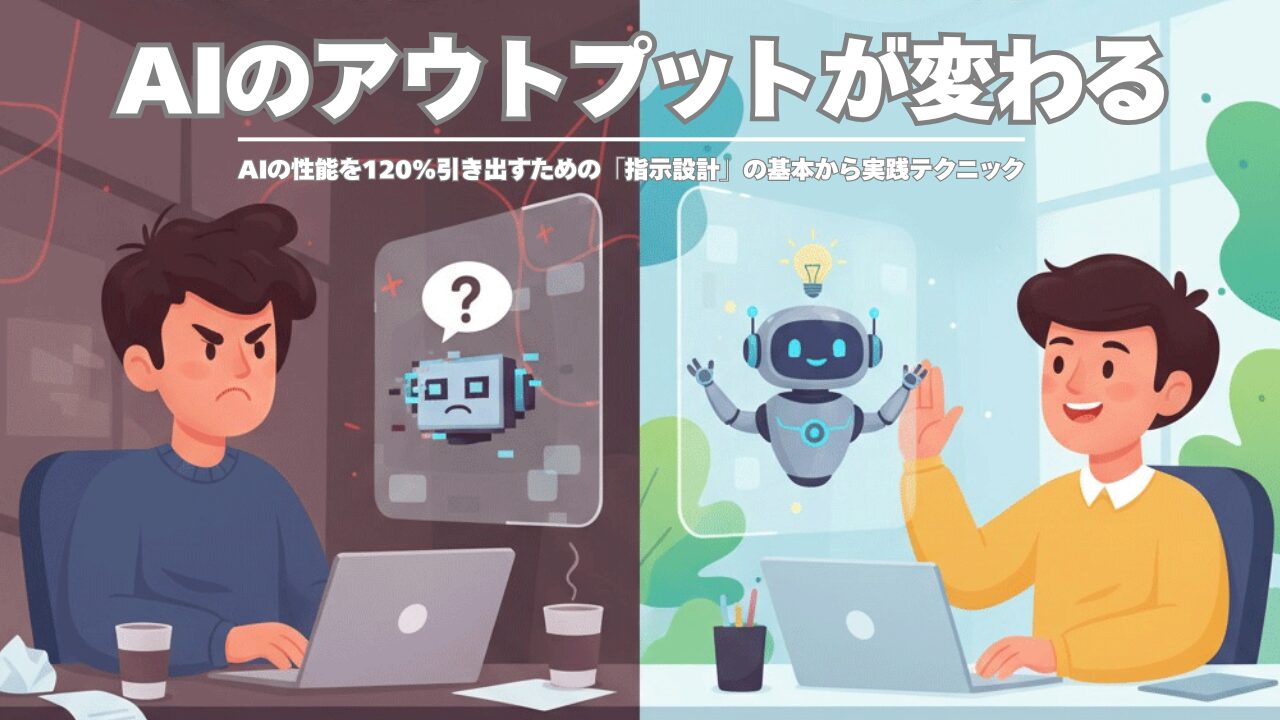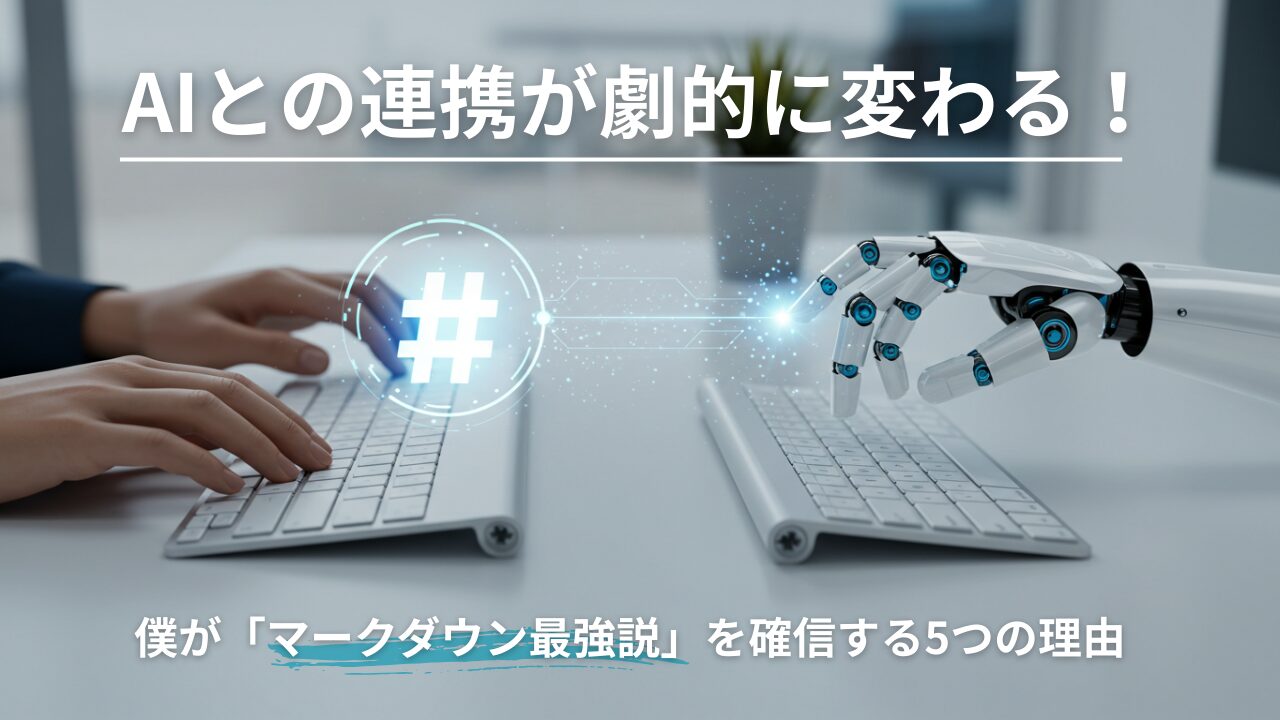「うわー…なんだこれ…マジか…」
深夜の作業部屋。AIに初めて触れたとき、僕の口から我ながら間抜けな声が漏れました。
目の前のモニターには、僕がたった数分前に入力した何気ない言葉(プロンプト)から生まれた、信じられないほど美しい風景画が映し出されていました。さらに別のツールにテキストを放り込むと、数秒で動画になり、さらには胸を打つような音楽まで奏で始めたのです。
鼓動が早くなり、手が冷たくなったように感じる。
これはただの「便利なツール」じゃない。何かが根本的に変わる瞬間に立ち会っている。直感的にそう感じました。
この胸の奥がザワザワして、いてもたってもいられなくなるような感覚。
「あれ?この感覚、どこかで…」
そう、それは四半世紀も前に、ブラウン管テレビの前でコントローラーを握りしめたまま体が固まった、あの日の衝撃にそっくりだったんです。
「そうだ、ミッドガルだ……」
1997年に『ファイナルファンタジー7』が僕らの世界を変えたように、今、AIが僕の止まっていた時間を、そしてクリエイティブの世界を、再び動かそうとしている。
この記事でわかること
- 僕がAIに感じている「革命的なワクワク感」の正体
- 25年前のファイナルファンタジー7が与えた衝撃との驚くべき共通点
- AIが「スキル格差」を破壊し、誰もがクリエイターになれる未来
- 僕のように一度は創作を諦めた人間が、再び夢を見始める方法
第1章:1997年、僕らの世界を変えた『ファイナルファンタジー7』という事件

あれは忘れもしない、1997年1月31日。
プレイステーションの電源を入れ、ディスクが回転する駆動音の後、静寂を破って映像が流れ始めました。
ゆっくりと流れる無数の星々。そして、緑色の妖しい光を放つ巨大な円盤型都市「ミッドガル」が画面いっぱいに映し出される。荘厳な音楽と共にカメラは街を舐めるように降下し、魔晄エネルギーを吸い上げる「魔晄炉」をかすめ、疾走する列車を捉える。やがて列車がホームに滑り込み、中から飛び出す数人のテロリスト。そして、最後に主人公、クラウドが飛び降りてくる――。
「え、これゲームなの?映画じゃなくて?」
当時の僕は、テレビの前で完全に心を奪われていました。
いや、正確に言うなら、僕の中の「当たり前」が音を立てて崩れ去った瞬間でした。
それまでの僕たちの知るゲームといえば、スーパーファミコンで描かれた温かみのあるドット絵の世界がすべてでした。キャラクターがカクカクと動き、想像力で補いながら物語に没入する。それが当たり前だったんです。
ところが、目の前では、まるでハリウッド映画のような美麗なCGムービーから、一切のロードを挟まずにシームレスに3Dポリゴンで描かれたゲームプレイへと移行していく。キャラクターはドット絵ではなく、立体的な「人間」としてそこに存在し、広大な3D空間を自由に駆け回る。
そして何より、植松伸夫氏による音楽が心の奥深くに響いて、僕を物語の世界へと引きずり込んでいく。気がつくと、僕はただの傍観者ではなく、クラウドと共にミッドガルの街を歩いてる錯覚を感じました。
あの瞬間、ゲームというエンターテイメントの次元が、僕の中で音を立てて変わったんです。それは単なるグラフィックの進化なんかじゃありませんでした。星の命運を巡る壮大なストーリー、心に刻まれる音楽、マテリアという画期的なカスタマイズシステム。すべてが一体となって、僕たちを「物語の世界に”いる”」という、今まで味わったことのない感覚に包み込んだのです。
「いつか自分も、こんな世界観を、物語を、自分の手で創ってみたい」
漠然と、しかし焦がれるほど強く、そう思ったのを今でも鮮明に覚えています。FF7は、僕にとってクリエイティブへの憧れを植え付けた、原体験そのものでした。
第2章:AIという、新しいクリエイティブの扉
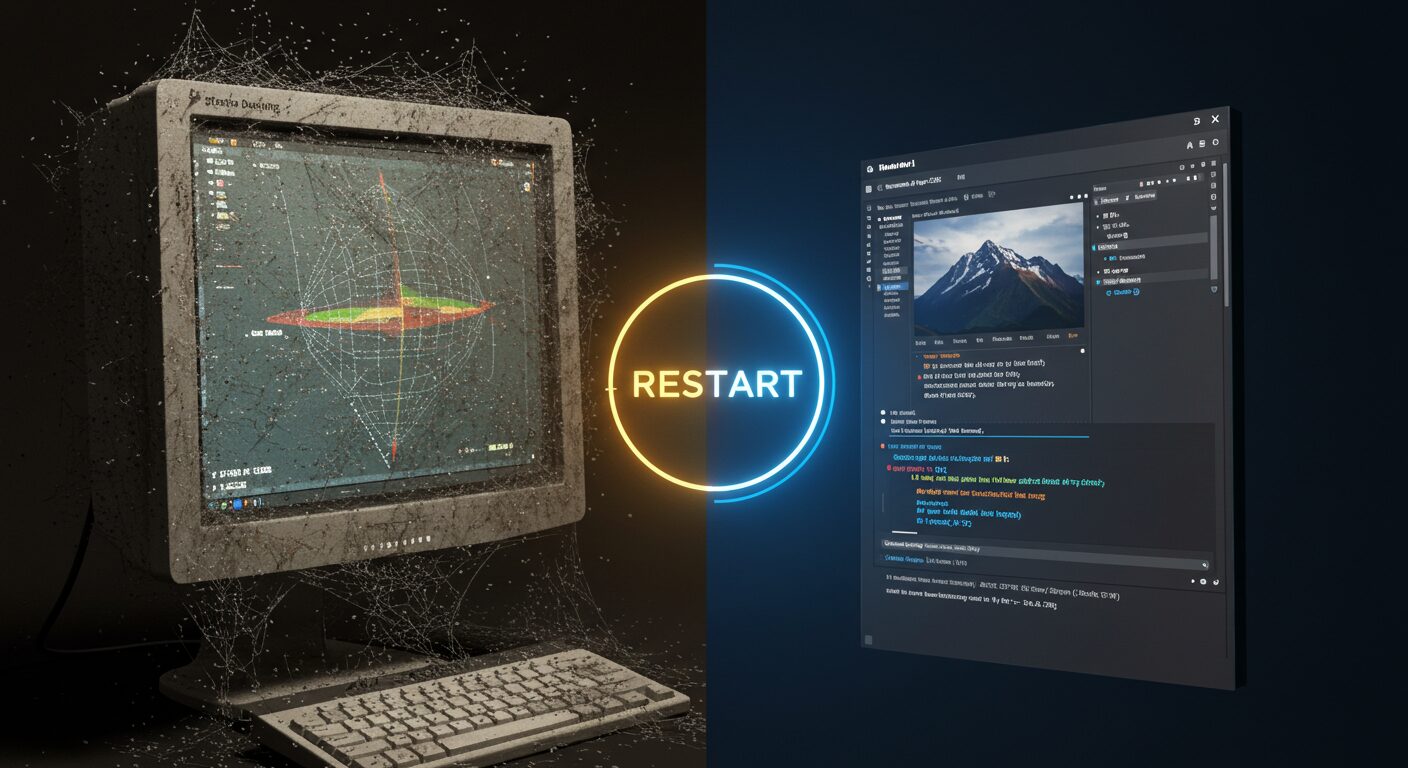
あれから長い年月が経ち、ゲームのグラフィックはあの頃のムービーを遥かに超えるものになりました。でも、最近僕が体験しているAIの進化は、それとはまったく質の違う「革命」だと感じています。
例えば、こんなことが現実になっています。
- 心に浮かんだイメージを言葉にするだけで、プロレベルのコンセプトアートが生まれる。
「サイバーパンクな東京の路地裏、雨上がりのネオン、孤独な少女のシルエット」と打ち込むだけで、映画のポスターのような美しいイラストが何枚も生成される。それも、たった数秒で。 - 複雑な3Dモデルを、AIが瞬時に補正し、美しく仕上げてくれる。
昔なら何時間もかけて調整していた光の反射や質感を、AIが「このほうがいいんじゃない?」と提案してくれる。まるで、隣に優秀なCGアーティストがいるみたい。 - プログラミングの知識がなくても、ゲームのロジックを組める。
「このキャラクターがジャンプボタンを押したら二段ジャンプするように」と自然な日本語で指示するだけで、きちんと動くコードが生成される。
一昔前なら、大きなスタジオで、大勢の専門家と膨大な時間をかけなければ作れなかったものが、今や個人のPCの中で、たった一人でも試せる時代になった。
これって、本当にすごくないですか?
僕があの時に夢見た「自分だけの物語を作りたい」という願いが、25年の時を経て、ようやく現実のものになろうとしているんです。
第3章:止まっていた夢が、再び動き出すワクワク感
FF7の衝撃に突き動かされ、僕は一時期、創作の世界に足を踏み入れました。特に3DCGに夢中になり、心許ない財布の中から『Vue』や『Shade3D』、『Poser』といったソフトを買い込み、見様見真似でモデリングに挑戦したんです。後には『Maya』や『ZBrush』『modo』といったプロ向けのツールにも手を出し、CGクリエイターのコミュニティで作品を発表し合ったりもしました。
最初の頃は楽しかったんです。少しずつキャラクターの形が見えてきたり、ライティングで雰囲気が変わったりする瞬間は、本当にワクワクしました。
でも、現実は甘くありませんでした。
- 専門知識という高すぎる壁:
モデリング、テクスチャリング、ライティング、レンダリング…覚えるべき専門用語と技術は膨大で、一つ一つの概念を理解するだけで頭がパンクしそう。参考書を読んでも、チュートリアル動画を見ても、「で、結局どうすればいいの?」という迷子状態が続く。 - 時間という残酷な現実:
たった一枚の静止画をレンダリングするのに、PCを一晩中唸らせ続けるなんてザラ。翌朝起きると「レンダリングエラー」の文字。キャラクター一体を納得いくまで作るのに数週間、数ヶ月とかかる。 - 才能という、どうしようもない差:
そして何より、圧倒的な才能を持つ人々の作品を前に、「自分には無理だ」という無力感に押しつぶされる日々。コミュニティで他の人の作品を見るたび、自分のちっぽけさを思い知らされる。
気がつくと、僕の机の上には使わなくなったCGソフトのパッケージが積み重なり、HDDには未完成のデータが眠り続けていました。
だから正直に言うと、FF7に憧れて抱いた「何かを創りたい」という夢は、いつの間にか心の奥底にしまい込んでいました。専門知識もないし、絵が描けるわけでもない。自分には無理だと、どこかで諦めていたんです。
FF7がくれたはずの輝かしい夢は、いつの間にかPCの奥底でホコリをかぶった「夢の残骸」になっていたんです。
でも、AIがその分厚い壁を、いとも簡単に壊してくれた。
「何言ってんだ、まだ終わってないだろ。やれよ。ほら、今度は俺が手伝ってやるよ」
そんな声が聞こえたような気がしました。
AIは、僕のような「アイデアはあるけどスキルがない」人間のための、最高の相棒になってくれる。プログラミングやモデリングといった専門技術のハードルを、魔法のように下げてくれるんです。
あの頃、「できたらいいな」と夢見ていたことが、今なら「よし、やってみよう」に変わる。25年間止まっていた時計の針が、再び動き始める音が聞こえる。確かに。
FF7のオープニングムービーを見て胸を熱くしたあの時から四半世紀の時を経て、AIという新しい武器を手に、再び創作のスタートラインに立てたのか・・・?
そう思うと、もうワクワクが止まらないんですよ。
第4章:AIは「魔法」か?いや、最高の「相棒」だ

もちろん、AIがすべてを自動でやってくれるわけではありません。
僕がこの数ヶ月間で学んだ大切なことは、AIは決して全自動の魔法の杖ではない、ということです。
最終的に何を生み出すかを決めるのは、いつだって僕たち人間。どんな世界を創りたいか、どんな物語を伝えたいか、どんな感情を揺さぶりたいか。それは僕たち一人一人のアイデアや、心の奥底にある想いによって決まります。AIはあくまで強力な道具であり、使いこなす側の創造性と情熱が問われるんです。
でも、その「使いこなす」過程すら、今はめちゃくちゃ楽しい。
自分の頭の中にある曖昧なイメージを、どういう言葉(プロンプト)にすればAIに伝わるのか?「もっと幻想的に」「少し寂しげな雰囲気で」「光をもう少し暖かく」…試行錯誤を繰り返し、AIとの対話を通じて、自分でも想像しなかったようなアウトプットが生まれた瞬間の快感。
「あ、これだ!これが僕の求めてた世界だ!」
そんな発見が、毎日のようにあるんです。これはもう、新しい形の創作活動そのもの。最高のエンターテイメントですよ。
FF7に「マテリア」というシステムがありましたよね。武器や防具に装着することで、魔法やアビリティが使えるようになる、あの画期的なシステムです。
僕にとってAIは、まさにあのマテリアのような存在。
今まで「絵が描けない」「プログラムが書けない」「音楽が作れない」といった理由でクリエイターになることを諦めていた人たちが、「画像生成AI」というマテリアを装着することでイラストレーターのように世界を描き、「音楽生成AI」というマテリアを装着することで作曲家のように心に響くメロディを紡げるようになる。
AIは、誰もが創造力を発揮できる「スキル格差なき世界」の扉を開けてくれたんです。
第5章:未来のクリエイターたちへ ― 僕たちが作る次の「衝撃」
もちろん、現段階のAI技術には、さまざまな課題があります。著作権の問題、フェイクニュースの懸念、悪用のリスクなど、解決すべき問題が山積みなのも事実です。僕たちユーザーも、技術の進歩に倫理観を追いつかせていく責任があります。
でも僕は信じています。いつかそういった課題がクリアになって、AIを当たり前に使える日がきっと来る。そしてその時、本当の革命が始まるのだと。
FF7が僕の人生に大きな影響を与え、その後の多くのゲームや映画に指標を示したように、今度は僕たちがAIを使って、次の世代の心を震わせる何かを創れるかもしれない。
どこかの誰かが、僕の作ったものを見て、あの日の僕がブラウン管の前で固まってしまったように、心を奪われてくれたら――。そして「自分も何かを作ってみたい」と思ってくれたら。
「うわー…なんだこれ…マジか…」
未来の誰かが、そんな間抜けな声を漏らしながら、新しい夢を抱いてくれたなら――。
そんな未来を想像すると、これからの毎日が楽しみで仕方ないんです。何者でもない僕が誰かを笑顔にできるかもしれない。誰かを感動させることができるかもしれない。そんな事ができたら素晴らしいと思いませんか。
僕たちの手の中には、もうAIという魔法のような道具があります。かつてFF7のクラウドがバスターソードを握りしめたように、僕たちはAIというペンを、筆を、カメラを握りしめている。
AIと創造力が融合するこの革命の時代に立ち会えた幸運に感謝しつつ、僕たちの手で、もっと面白くて、もっと人間らしい、新しい未来を作っていけたら。
25年前、FF7が僕たちにくれた衝撃を、今度は僕たちが誰かに届けたい。そう思うんだ。