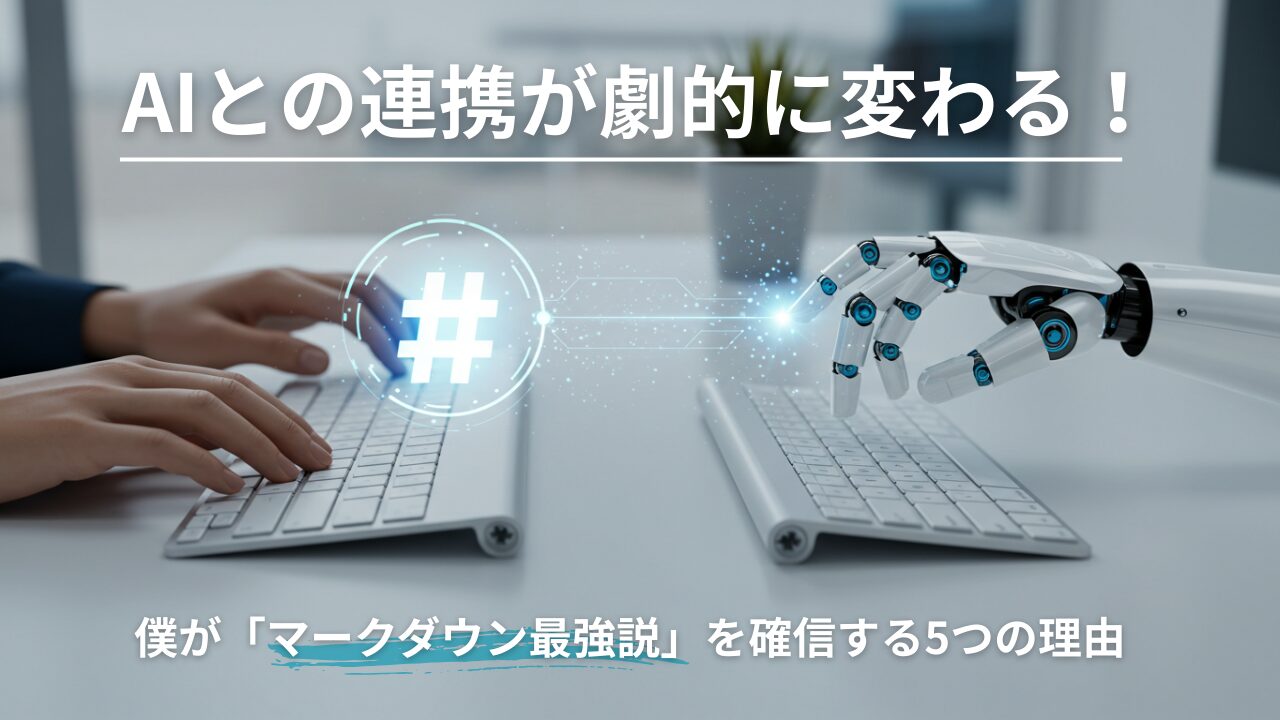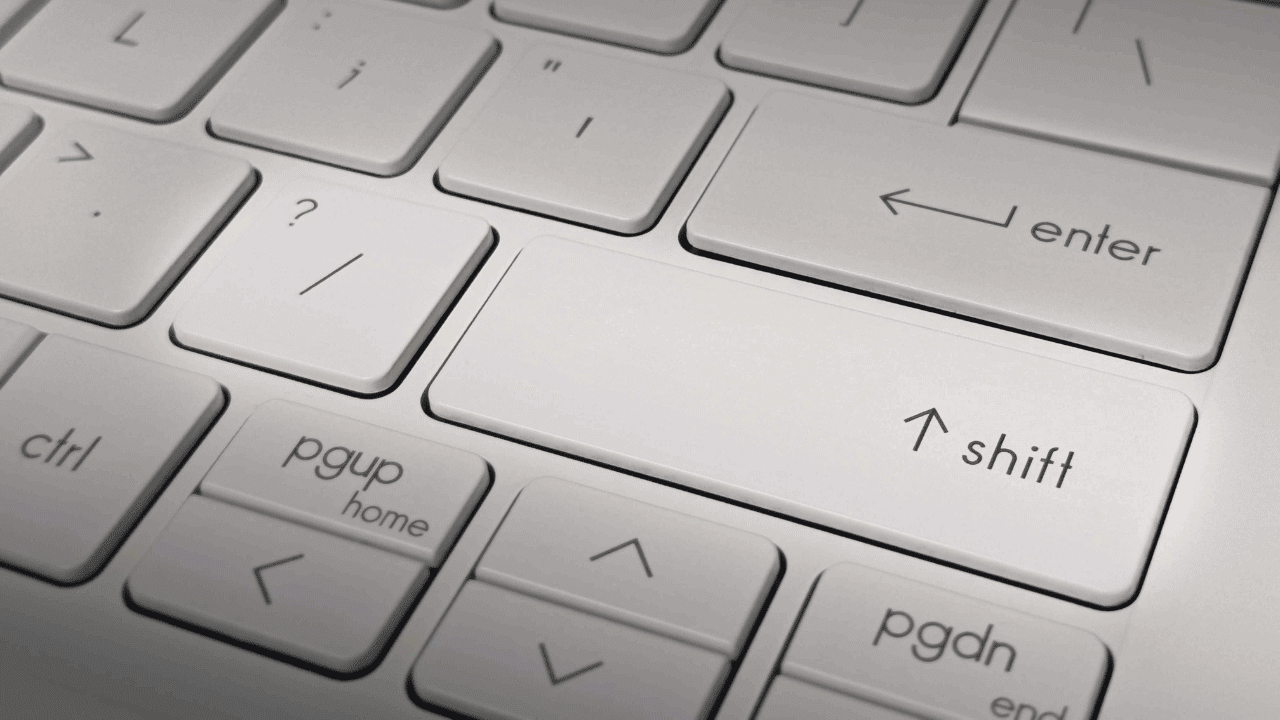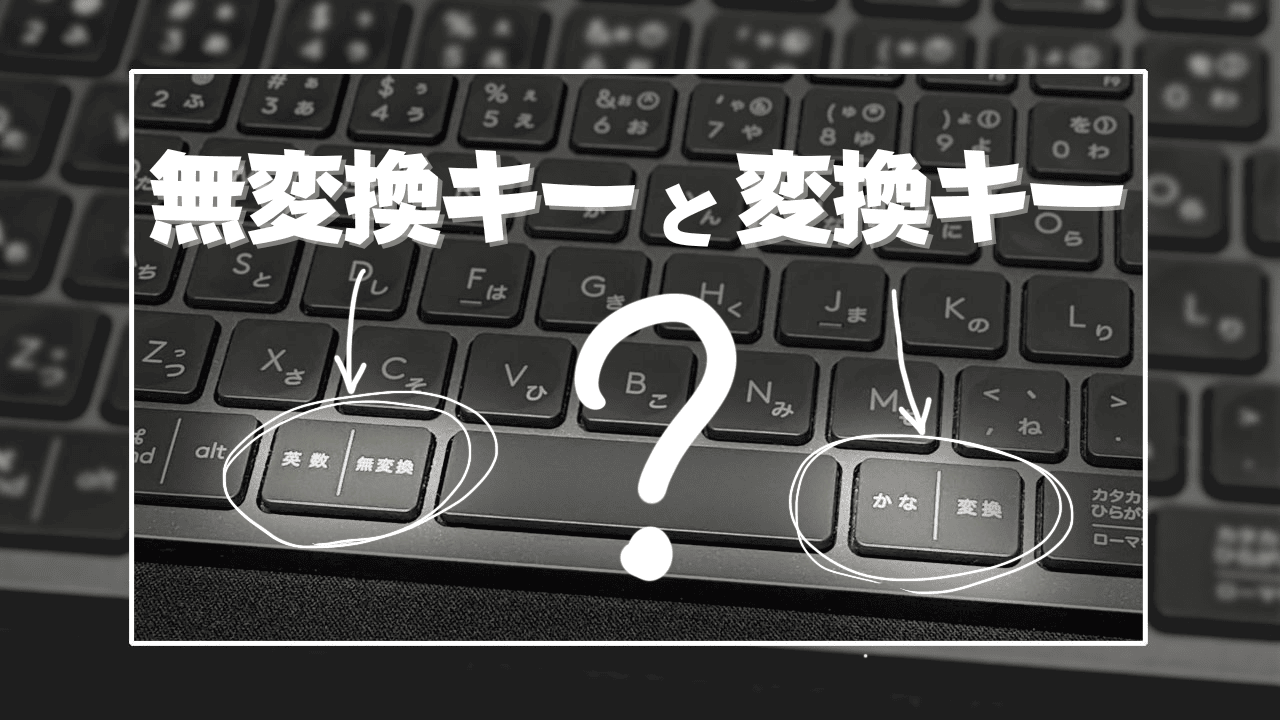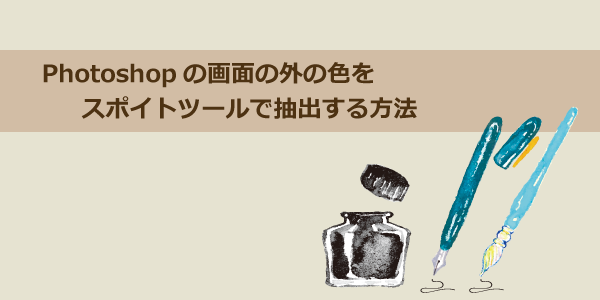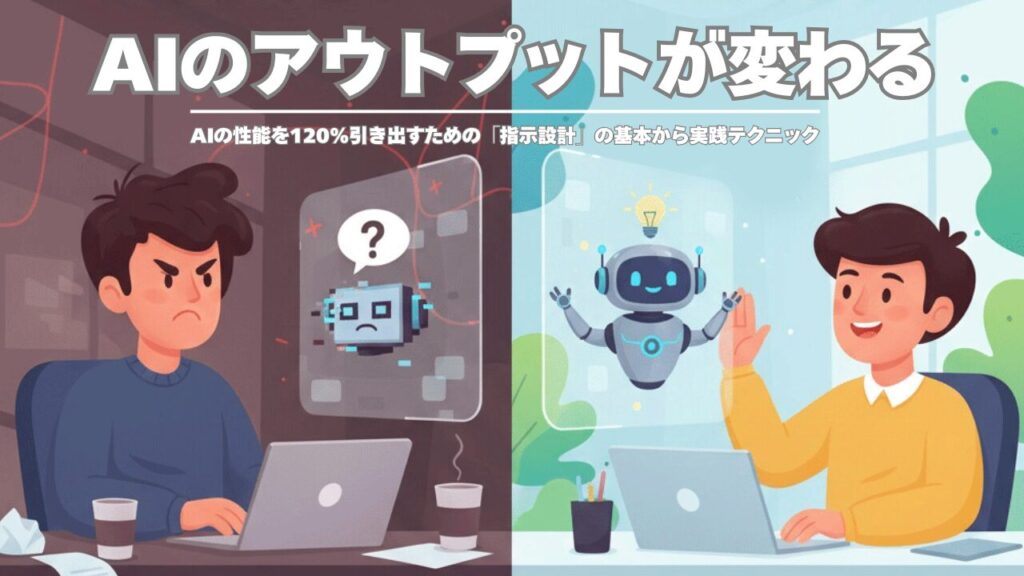
「AIに頼んだのに、ぜんぜん思った通りに動いてくれない…」
「AIにブログ記事を頼んだら、当たり障りのない文章しか出てこない…」
「このニュアンス、どうやったら伝わるんだ…?」
最近、ChatGPTやGeminiのようなAIツールが当たり前になってきた一方で、多くの人がこんな「AIとのコミュニケーションギャップ」に悩んでいるんじゃないでしょうか。
僕も最初はそうでした。「ブログ記事を書いて」と一言だけ投げてみては、当たり障りのない、魂のこもっていない文章が返ってきて、がっかりすることの繰り返し。正直、「AIって、この程度か…」なんて思ってしまった時期もありました。
それからも、毎日AIと対話していますが、いまだに「そうじゃないんだよなぁ…」と頭を抱えることがあります。
でも、ある時ふと気づいたんです。これって、AIが悪いんじゃない。使う側の指示の出し方に問題があるんだって。
この記事では、AIを「魔法の杖」だと勘違いして失敗しがちな「丸投げ」状態から抜け出し、AIをまるで「超優秀な部下」のように育て上げ、最高のパフォーマンスを引き出すための「指示設計スキル」について、僕自身の失敗談も交えながら語っていきます。
この記事でわかること
- なぜAIとの間に「なんで分かってくれないの?」というギャップが生まれるのか
- AIがあなたの意図を120%理解してくれる「指示設計」の基本
- 明日からすぐに使える、具体的な指示のテクニック10選
- AIは「育てる」ものだという、新しい付き合い方
第1章:なぜ僕たちの「普通」はAIに通用しないのか?
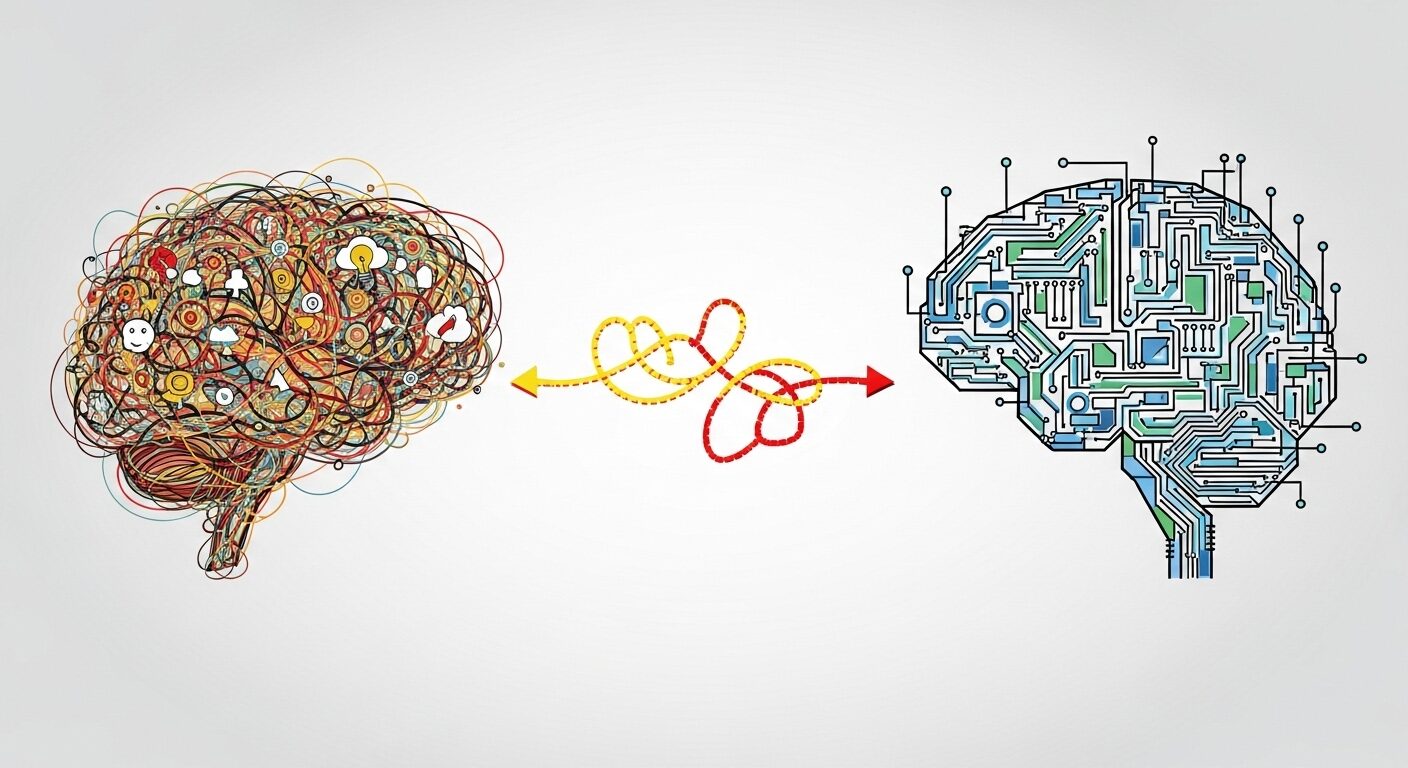
人間同士の会話って、不思議ですよね。「あれ、やっといて」とか「いい感じにしといて」みたいな、主語も目的も曖昧な言葉でも、なぜか意図が伝わってしまう。「あうんの呼吸」ってやつです。
でも、この日本特有のハイコンテクストなコミュニケーションは、残念ながらAIには一切通用しません。
- 曖昧な表現:「いい感じに」→ 何がどうなれば「いい感じ」?
- 主語の省略:「ブログ書いといて」→ 誰が、誰に向けて、何について?
AIは、僕たちが頭の中で「当然こうでしょ」と思っている前提知識や文脈を共有していません。彼らにとっての世界は、僕たちがインプットした言葉(データ)がすべて。だから、言葉が足りなかったり、曖昧だったりすると、AIは混乱してしまうんです。
「今日の会議のまとめ、よろしく」と人間に頼めば、
- どの会議か
- 誰に共有するためか
- どのくらいの粒度でまとめるべきか
といったことを、過去の経験から推測してくれます。でもAIに同じことを頼んだら、「どの会議ですか?」「誰向けの要約ですか?」「箇条書きにしますか?文章にしますか?」と質問攻めに合うか、あるいは見当違いなアウトプットを返してくるのがオチ。
この 「僕たちの常識」と「AIの知識」のズレこそが、「なんで分かってくれないの?」の正体なんです。
第2章:AIを動かす心臓部!「指示設計」の基本のキ
じゃあ、どうすればAIに意図通りに動いてもらえるのか。その答えが 「指示設計」です。
「指示設計」なんて言うと難しく聞こえるかもしれませんが、要は 「ゴールを明確にして、そこまでの地図を渡してあげる」 作業です。
僕はいつも、AIを 「やる気はあるけど、まだ右も左も分からない新人部下」 だと思って接しています。この新人君に最高のパフォーマンスを発揮してもらうために、デキる上司として的確な指示書を渡してあげればいい。
要は、「AIにやってほしいことを、誤解なく、具体的に伝える技術」ですね。僕はこれを、「入力 → 処理 → 出力」の3ステップで考えるようにしています。
- 入力(Input):
AIにどんな情報やデータを与えるか?(例:この記事のテーマ、キーワード、参考資料) - 処理(Process):
AIにどんな作業を、どんな条件で実行してほしいか?(例:ブログ記事を書いて、ターゲットは初心者、親しみやすい文体で) - 出力(Output):
どんな形式で成果物を出してほしいか?(例:Markdown形式で、4000字以上、タイトルと見出し付きで)
この3つを意識して、「誰に、何を、どうしてほしいのか」を明確に言語化してあげる。たったこれだけで、AIの反応は劇的に変わります。これはもう、魔法と言ってもいいレベルです。
第3章:実践テクニック10選|これを押さえれば、あなたもAIマスター!

では、具体的にどう指示すればいいのか。僕が普段、実践しているテクニックを10個、一挙にご紹介します!
- ゴールを一言で伝える
最初に「この記事の目的は、〇〇です」と結論を伝えましょう。AIも目的が分かると、仕事の精度が格段に上がります。 - 対象読者・用途を明記する
「誰が読むのか」「何に使うのか」は超重要です。「30代の男性会社員向け」「社内プレゼン用資料」など、具体的に指定しましょう。 - トーンや文体を指定する
「友達に語りかけるようなカジュアルな感じで」「専門家としての信頼感が伝わる論文調で」など、人格や文体を指定すると、アウトプットの雰囲気をコントロールできます。僕のブログ記事をAIに手伝ってもらう時は、このガイドラインを伝えています。 - 文字数や構成の条件を加える
「3000字程度で」「導入・本編・まとめの3部構成で」「箇条書きを3つ以上入れて」など、具体的な制約を入れることで、アウトプットの型を固定できます。 - 参考になるフォーマットや例を見せる
「この文書みたいな構成と雰囲気で」「以下の例文のトーンを真似て」と、お手本を見せるのが一番の近道。AIは模倣の天才です。 - 「やってほしくないこと」も伝える
「専門用語は使わないで」「ネガティブな表現は避けて」のように、禁止事項を伝えることで、失敗を未然に防げます。 - 前提条件・背景情報を共有する
「このプロジェクトは、〇〇という課題を解決するために始まりました」といった背景情報を与えると、AIは文脈を深く理解し、より気の利いた提案をしてくれるようになります。ここが結構影響するかなと感じています。 - 一度に詰め込みすぎない(分割して伝える)
複雑な依頼は、一度に全部やらせようとせず、「まず構成案を出して」「次に導入部分を書いて」と、タスクを分解して少しずつ進めるのが成功のコツです。 - フィードバックして改善させる(再指示)
一発で完璧な答えを求めないこと。「もっと感情的な表現を増やして」「この部分は、もっと具体例を交えて書き直して」のように、対話しながら理想の形に近づけていくのが正解です。 - プロンプトテンプレートを活用する
毎回ゼロから指示を考えるのは大変です。よく使う指示はテンプレート化して保存しておきましょう。Geminiの「Gem」機能などは、まさにこのためにあると言っても過言ではありません。
第4章:ビフォーアフターで学ぶ!ダメな指示、イケてる指示
百聞は一見に如かず。僕が実際にやってしまった失敗例と、改善後の例を見てみましょう。
例:ブログ記事のタイトル作成
【ビフォー】ダメな指示
AI活用についてのブログ記事のタイトルを考えて。
→ 出てくるアウトプット
- AIの活用方法
- AIを仕事に活かすには
- これからのAI時代
(うーん、普通すぎる…)
【アフター】良い指示
# ブログタイトル作成依頼
## テーマ
AIが指示を理解してくれない根本原因は、実は「使う側の指示の出し方」にある、という気づきを与えるブログ。## ターゲット
AIを使い始めたけど、いまいち使いこなせていないと感じるビジネスパーソン。## 含めてほしいキーワード
「AI」「部下」「指示」「なぜ」## トーン
少し挑発的で、読者が「自分のことかも?」とドキッとするような感じ。## 条件
3つ提案してください。
→ 出てくるアウトプット
- 【衝撃】あなたのAIがポンコツなのは、能力のせいじゃない。問題はあなたの「指示」にあった。
- 「なんで分かってくれないの?」はもう終わり。AIを“言われたことしかできない部下”から“最高の相棒”に変える指示術。
- その指示、AIに届いてますか?優秀なAIをダメにする「残念な上司」になっていないか、今すぐチェック。
(おぉ、これこれ!って感じですよね!)
第5章:AIは「育てる」相棒だ

僕たちはつい、AIを「完璧な答えを出す魔法の箱」のように考えてしまいがちです。でも、それは大きな間違い。
AIは、「対話を通じて、自分色に染めていく、育てる相棒」なんです。
最初は意図を汲み取ってくれなくても、根気強くフィードバックを繰り返すことで、AIは「あ、この人はこういう表現が好きなんだな」「この話題の時は、この情報を求めているんだな」と学習し、どんどんあなた好みの、気の利くパートナーへと成長していきます。
日々のやり取りすべてが、AIの教育になっている。そう考えると、AIとのコミュニケーションが、なんだか育成ゲームみたいで楽しくなってきませんか?
まとめ:AIとの信頼関係は「言葉」から始まる
AIを使いこなせるかどうかは、ツールの性能以上に、ボクたち使う側の「指示設計能力」、つまり 「言葉をどう選び、どう構造化して伝えるか」 にかかっています。
AIとの連携やメモ書きに非効率を感じていませんか?本記事では、なぜ「マークダウン」がAI時代の必須スキルなのか、その理由と具体的な活用法を初心者向けに徹底解説。あなたの知的生産性を劇的に向上させます。
AIは、対話を重ねることで、あなたの好みや思考のクセを学習していきます。何度もフィードバックを与え、修正を繰り返すことで、次第に「あうんの呼吸」で仕事ができる、あなただけの最高のパートナーに育っていくんです。
AIとのコミュニケーションは、人間関係と同じ。相手を理解しようと努め、丁寧に言葉を尽くすことで、初めて良い関係が築けます。
AIは、あなたの言葉を待っています。さあ、今日から「デキる先輩」として、AIという超優秀な新人との対話を楽しんでみませんか? その一歩が、あなたの仕事や創造の可能性を、無限に広げてくれるはずですから。
以上です。この記事が少しでも参考になれば幸いです。
—–
このブログではテレワークやパソコンを使って自宅で仕事をするために役立つ小ネタを多数紹介しています。Twitterでも情報発信していますので、今回の記事が役立ったよ!と思ったらTwitterでいいね&フォローお願いします!
Twitter: @tele_commuter