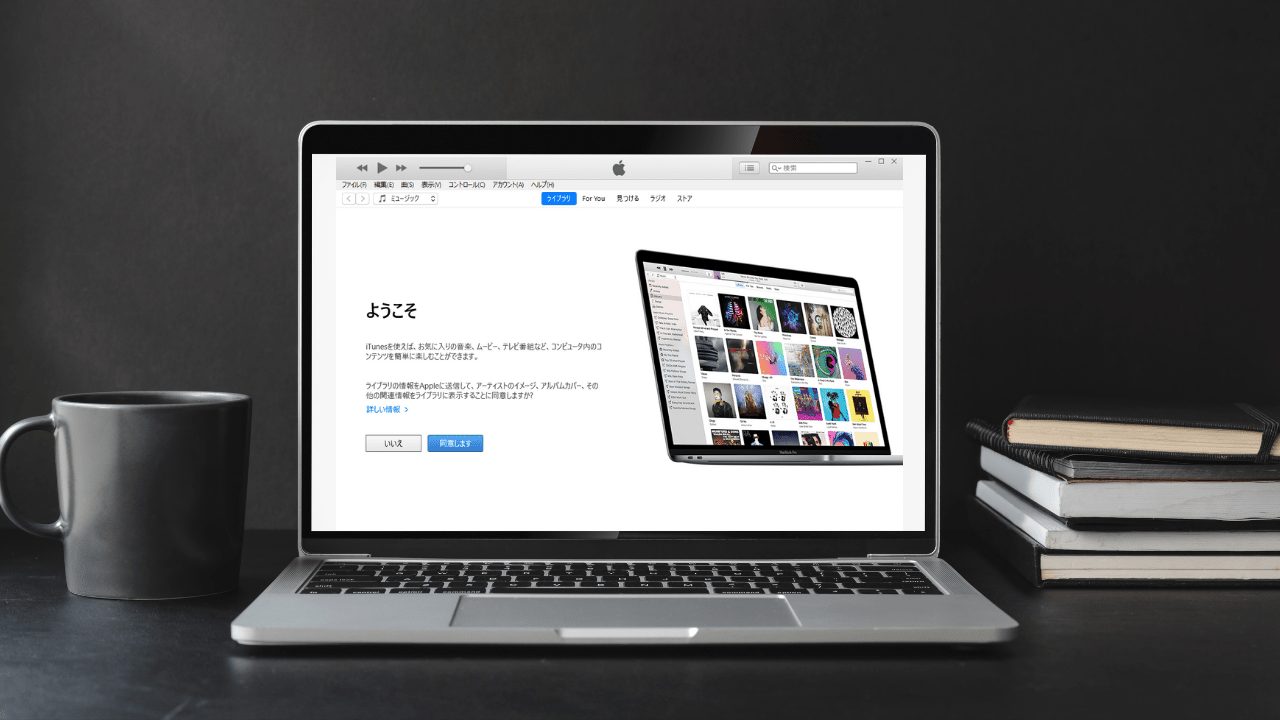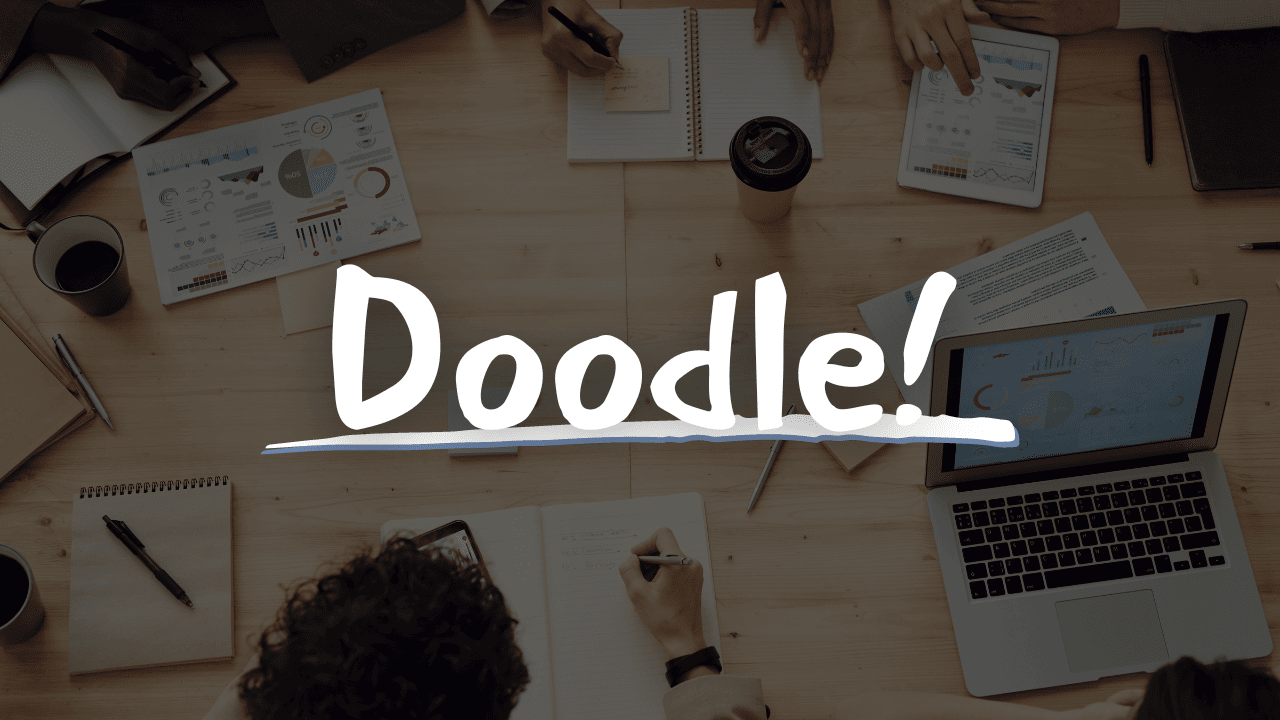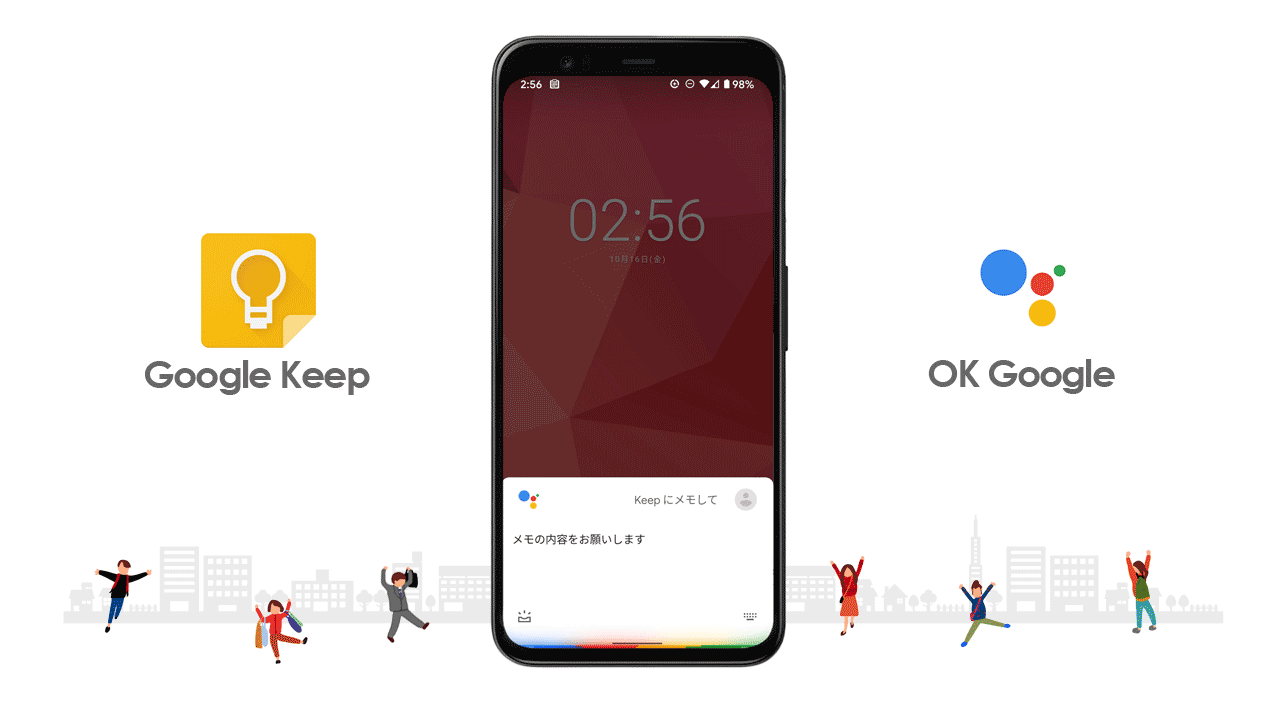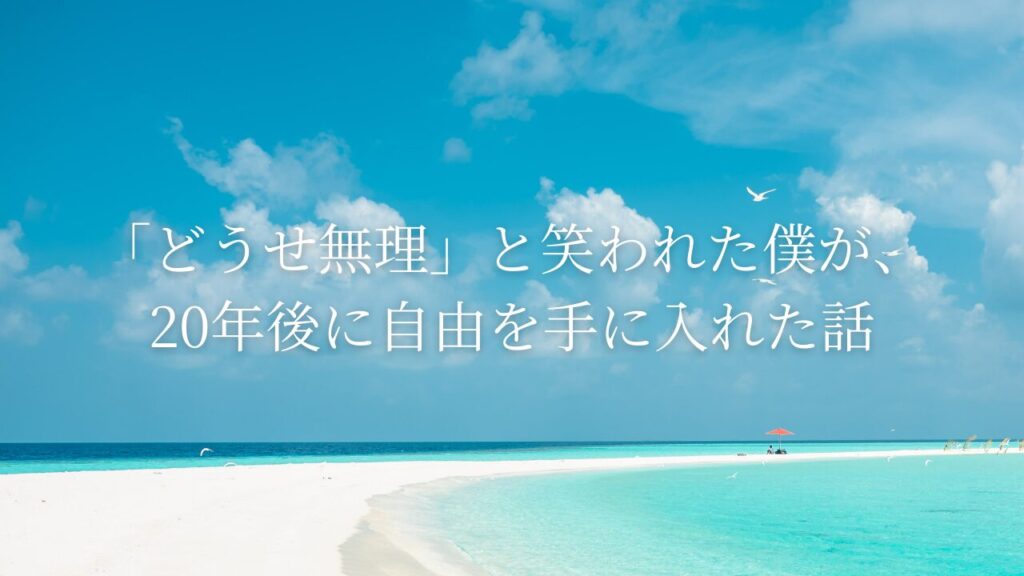
「何かに挑戦したい」
そう思ったとき、あなたの周りにどんな反応をする人が多いですか?
「すごいね!応援するよ!」
そう言ってくれる人もいれば、
「フッ、甘いこと言ってるよw」
と、まるで夢物語かのように鼻で笑う人も、残念ながらいるのが現実です。
僕の場合もその後者でした。
今でこそ、アフィリエイトというビジネスモデルのおかげで、時間や場所に縛られずに働くという、いわゆる「自由な生活」を手に入れることができましたが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。特に、僕が「これだ!」と将来性を感じて熱中したアフィリエイトという世界は、当時は今よりもずっと怪しいものだと見られていたんです。
寝る間も惜しんで試行錯誤を繰り返す僕に、知人は言いました。
「ああ、あの胡散臭いバナー広告のやつだろ?」
また、ある人は、何か勧誘されるとでも思ったのか、あからさまに距離を置いていきました。
悔しくて、悲しかった。でも、僕は心のどこかで確信していたんです。「この道は間違っていない」と。だから、表立ってアフィリエイトの話をすることはなくなりましたが、それでも、たった一人、諦めずにずっと続けてきました。
そして20年後。もしあの時、「やっぱり自分には無理なのかもしれない」と諦めていたら、今のこの自由な生活はありませんでした。
実際には20年かかったわけではなくて、数年で安定した状態まで持っていけて、20年以上維持しているという感じです。
あの時、僕を笑った人たちが今どうしているか僕は知りません。でも、僕はあの時信じた道を突き進んだからこそ、今の自分がある。これだけは、胸を張って言えます。
この記事は、過去の僕のように、何か新しい挑戦を始めようとしているけど、周りの目が気になって一歩を踏み出せないでいる「あなた」に向けて書いています。
この記事でわかること
- なぜ、あなたの挑戦を笑う人が現れるのか?
- 「想像できることは実現できる」という言葉の本当の意味
- 失敗を恐れる心が、どれだけ成功を遠ざけているか
- 成功への最短ルートである「見切り発車」という最強の武器
もし、あなたが今、少しでも迷いや不安を抱えているなら、どうかこの記事を最後まで読んでみてください。きっと、あなたの背中を強く押す、何かが見つかるはずです。
第1章:なぜ挑戦は笑われるのか?それでも、あなたの心の声を信じるべき理由

そもそも、なぜ新しい挑戦は他人に笑われたり、反対されたりすることが多いのでしょうか。
それは、多くの人が 「変化を恐れる」からなのでしょう。あなたが新しい挑戦をすることで、今いるコミュニティの常識や均衡が崩れるように感じてしまう。あるいは、あなたが成功してしまったら、自分が今の場所に留まっていることが「間違い」だったように思えてしまう。そんな無意識の恐怖が、「どうせ無理だよ」という言葉に変わるのでしょう。
彼らは、あなたの可能性を否定したいわけではありません。ただ、自分の安心を守りたいだけなのです。
例えば、今をときめくギタリストだって、最初はコードがうまく押さえられず、指から血を流した日があったはずです。世界的なピアニストだって、バイエルを何度も間違え、泣きながら練習した夜があったでしょう。誰もが尊敬するイラストレーターも、スポーツ選手も、最初はみんな、何もできない「素人」だったのだと思います。
彼らがプロになれたのは、才能があったからだけではありません。
「それでも、自分はこの道が好きだ。この先に未来があると信じている」
そんな心の声を信じ、周りの雑音に耳を貸さず、ただひたすらに練習を続けたからです。
あなたの挑戦を笑う声は、いわば「通りすがりのノイズ」のようなもの。あなたの人生の責任を取ってくれるわけでは決してありません。本当に耳を傾けるべきは、あなた自身の「こうなりたい」「これをやってみたい」という、内なる声です。
第2章:「想像できることは実現できる」は、ただの精神論じゃない
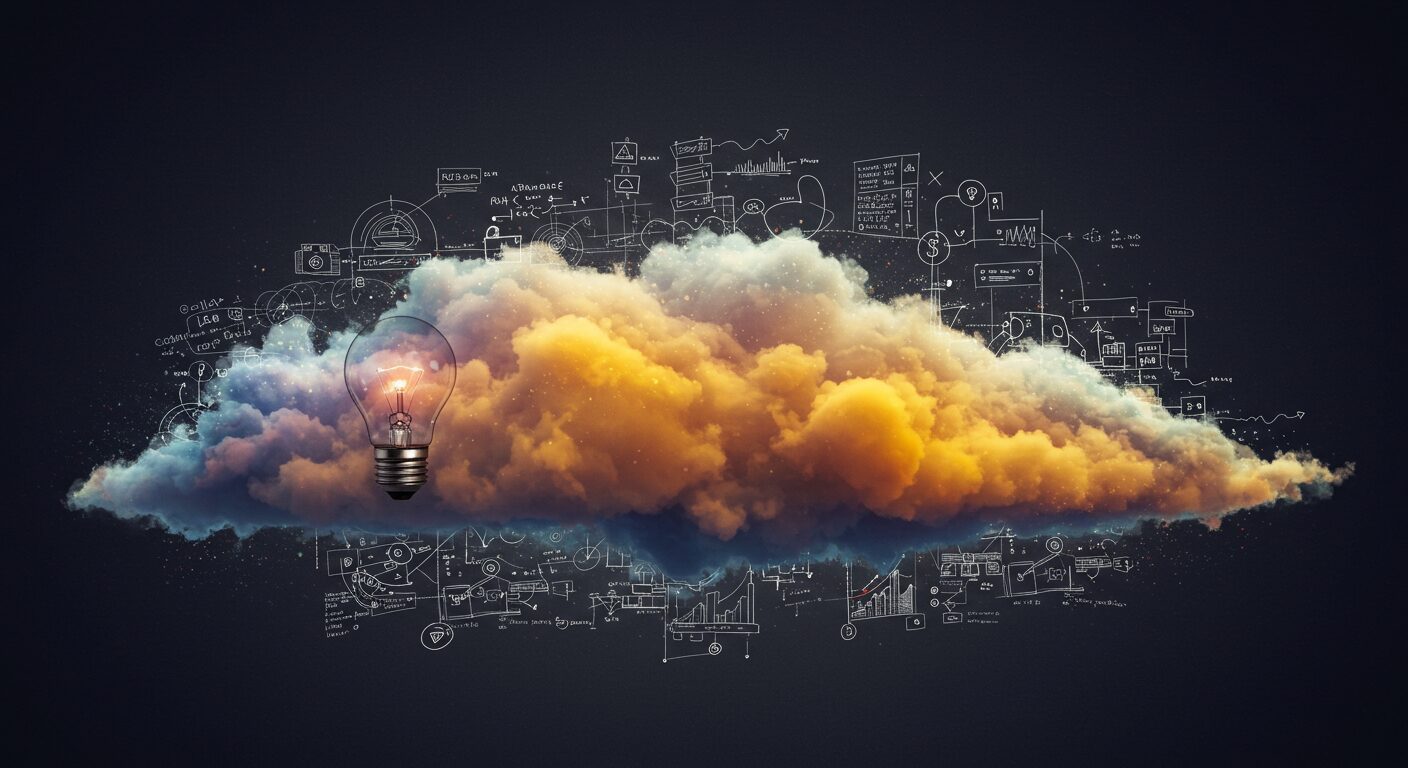
「人間はできないことは想像できない。逆に言えば、想像できることは実現可能だ」
これは、僕が大切にしている言葉の一つです。
「そんなの、ただの綺麗事じゃないか」と思うかもしれません。でも、これは脳科学や心理学の観点からも、理にかなっているそうです。
あなたが「こうなれたらいいな」とおぼろげにでも想像できるということは、あなたの脳が、そのゴールに至るまでの道筋を無意識レベルで探し始めている証拠です。
例えば、「赤い車が欲しいな」と思った瞬間から、街中でやたらと赤い車が目につくようになった、という経験はありませんか?これは「カラーバス効果」と呼ばれる現象で、脳が特定の情報を意識し始めると、関連する情報が自然と集まってくるようになるのです。
その「おぼろげな成功の姿」こそが、あなたの進むべき道を示すコンパスになります。
例えば、あなたが「いつか自分のブログで生計を立てたい」と想像したとします。その瞬間、あなたの頭の中には、たとえおぼろげでも「成功した自分の姿」が映し出されているはずです。
それは、記事を書いている姿かもしれないし、読者から感謝のコメントをもらっている場面かもしれません。あるいは、好きな場所で好きな時間に仕事をしている自由なライフスタイルかもしれません。
多くの人は、そのぼんやりとしたイメージに対して、「でも、文章力がないし…」「時間もないし…」「何を書けばいいか分からないし…」と、次々に「できない理由」を探し始めます。まるで、自分で自分の夢にブレーキをかけているかのようです。
でも、考えてみてください。その「できない理由」は、本当に乗り越えられない壁でしょうか?
- 文章力がない → 毎日少しずつ書く練習をすればいい。AIにサポートしてもらうことだってできる。
- 時間がない → 通勤電車の中の15分、寝る前の30分から始めてみればいい。
- 何を書けばいいか分からない → 自分が好きなこと、得意なこと、悩んだことを発信することから始めてみればいい。
ほら、少し視点を変えるだけで、「できない理由」は「どうすればできるか?」という具体的な課題に変わります。
「できない理由」を数えるのではなく、「できる理由」を一つずつ拾い集めていく。
それが僕がずっと続けているマインドセットです。
ゴールが決まれば、あとは逆算して道筋を立てて、実行していくだけ。自分で立てる計画なんだから、無理なく進めるように計画すればいいんです。そうすれば、歩みは遅くても必ず前に進めるはずです。
第3章:失敗は「悪」じゃない!成長を爆速化させる「改善点」という名の宝物
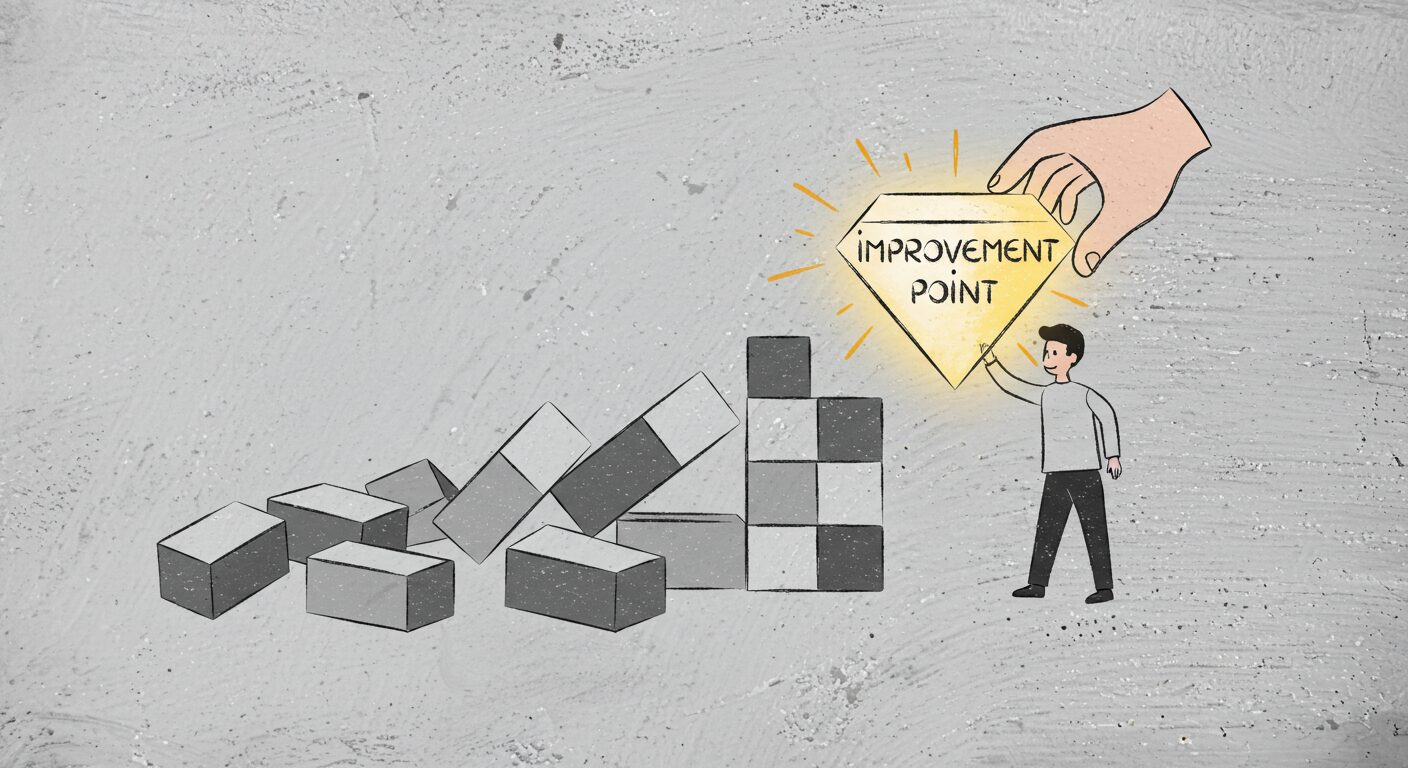
多くの人が、最短距離で成功したがります。気持ちはとてもよく分かります。誰だって、無駄な努力はしたくないし、失敗して恥ずかしい思いもしたくないですよね。
でも、断言します。失敗を避けて通る成功など、ありえません。
むしろ、失敗こそが、あなたを誰よりも早く成長させてくれる「最高の燃料」なんです。
「失敗したらラッキー!」というのは言い過ぎですが、失敗するからこそ見える景色が必ずあります。
なぜなら、失敗するからこそ、
- 「このやり方は、うまくいかないんだな」
- 「次は、こう変えてみよう」
という、具体的な 「改善点」が見つかるからです。
改善点があるということは、そこに「伸びしろ」があるということ。つまり、あなたはまだ、もっともっと成長できるということです。
考えてみてください。ゲームで一度もゲームオーバーにならずにラスボスまでたどり着けるでしょうか?おそらく、何度も敵にやられ、そのたびに「この敵には、この武器が有効なのか」「ここで回復アイテムを使うべきだった」と学び、少しずつ上達していくはずです。
挑戦も、それと全く同じ。
- ブログ記事を書いたけど、全然読まれなかった。
- → 改善点:タイトルが魅力的じゃなかった?導入で離脱された?もっと読者の悩みに寄り添うべき?
- イラストを投稿したけど、「いいね」がつかなかった。
- → 改善点:もっと魅力的な構図がある?色の使い方が単調?ハッシュタグの選び方が悪かった?
少々の失敗なんて、かすり傷と同じです。恐れる必要は全くありません。
とりあえず、やってみる。
そして、改善する。
仮説 > 実行 > 検証 > 改善
いわゆる「PDCA」サイクルですよね。
このサイクルを、どれだけ早く、どれだけ多く回せるか。これこそが、凡人が天才に勝てる、唯一にして最強の戦略なのです。
第4章:成功への最短ルートは「見切り発車」にあり

「失敗してもいいのは分かった。でも、やっぱり怖いから、しっかり勉強して、完璧に準備ができてから始めたい」
その気持ち、痛いほど分かります。でも、あえて厳しいことを言います。その「完璧な準備」が整う日は、永遠に来ません。
なぜなら、あなたが勉強している間にも、状況は刻一刻と変化していくからです。Webの世界なら、新しいサービスが生まれ、アルゴリズムが変わり、トレンドが目まぐるしく移り変わります。あなたが「完璧だ」と思った知識は、行動に移す頃にはもう時代遅れになっているかもしれないのです。
では、どうすればいいのか?
答えはシンプルです。「見切り発車」すること。
見切り発車過ぎるのは問題ですが、そこそこの理解でいい。60点、70点でいい。とにかく行動を始めてしまうのです。
- ブログの立ち上げ方が完璧に分からなくても、とりあえずサーバーを契約してみる。
- 文章術の本を全部読まなくても、まず1記事、自分の言葉で書いてみる。
- イラストの描き方が分からなくても、まず1枚、最後まで仕上げて投稿してみる。
やってみれば、必ず壁にぶつかります。分からないことが出てきます。でも、それでいいんです。その「分からないこと」こそが、あなたが今、本当に学ぶべきことだからです。
もちろん、最低限の知識や準備は必要です。しかし、多くの人は「準備」という名の「行動しない言い訳」に時間を使いすぎています。
僕は運送業も経営しているのですが、夏期や冬期の繁忙期には多くのアルバイトさんに手伝ってもらっています。その中で、慎重になりすぎて準備に時間をかけすぎる人と、最低限の仕度はしっかりとやってとりあえず配達に出るという人では、圧倒的に後者の方が稼ぐ金額が大きいです。
僕が尊敬する経営者やクリエイターは、皆そろって「見切り発車」の達人です。彼らは、70%くらいの完成度で見切り発車し、世の中の反応を見ながら残りの30%を創り上げていきます。
机の上で10時間勉強するより、たった1時間、実践で試行錯誤する方が、何倍も濃密な学びが得られます。未熟な部分は、後からいくらでも修正できます。走りながら考え、学び、修正していく。
なぜなら、机の上でどれだけ完璧な計画を練っても、実際にやってみなければ分からないことだらけだからです。
- 読者が本当に求めているものは何か?
- 市場がどう反応するか?
- どこに思わぬ落とし穴があるのか?
これらはすべて、行動した人にしか見えない景色です。
これこそが、変化の激しい現代において、最速で結果を出すための唯一の方法論なのです。
行動だけが、現実を変える唯一の力です。
まとめ:あなたの物語は、今日この一歩から始まる
20年前、周りに笑われながらも、僕は小さな一歩を踏み出しました。その一歩が、また次の一歩を生み、気づけば20年という月日が経っていました。そして、あの頃は想像もできなかった景色が、今、目の前に広がっています。
あなたにも、きっとあるはずです。
心の奥底で、ずっとやりたいと思っていることが。
「どうせ自分には無理だ」と、蓋をしてしまっている夢が。
大丈夫。
想像できるなら、それは必ず実現できます。
失敗は、あなたを強くしてくれる最高の経験値です。
完璧じゃなくていい。小さな一歩を踏み出してみてください。
その一歩が、1年後、5年後、10年後のあなたを、今のあなたが想像もできないような、素晴らしい場所へと連れて行ってくれるはずだから。
あなたの挑戦を、心から応援しています。
—–
ところで、僕には今、本気でやりたいことが2つあります。
例によって、周りからは「また何か変なこと言ってるよ」と、あからさまに呆れられています。でも、僕はやります。絶対に。
誰かに迷惑をかけるわけじゃない。僕が僕の人生をかけて追い求める、純粋な夢なんですから。
そして、数年後には必ず実現させてみせます。
なぜなら、僕の頭の中には、その夢が叶ったときの景色が、もうハッキリと見えているからです。
そう、想像できる未来は、実現可能だ!
書籍おすすめ
挑戦を笑う声に惑わされず、夢を現実に変えるには「できない理由」ではなく「できる理由」を数え、自分の小さな一歩を踏み出すマインドセットが不可欠です。
そして、完璧な準備より先に「見切り発車」して行動し、失敗を「改善点」という宝物に変える姿勢が成功への最短ルート。
今回ご紹介した書籍は、きっとあなたの挑戦を支え、背中を押してくれる大きな味方になるでしょう。
こうして、夢は現実になる(パム・グラウト 著)
夢を実現するための思考法をやさしく解説。想像できることは実現可能という考え方を深め、前向きな挑戦を後押ししてくれます。
思考は現実化する(ナポレオン・ヒル 著)
成功哲学のクラシックで、願望設定から行動計画、忍耐力まで、夢を形にするために必要な考え方が体系的に学べます。たくさんの人が関連書籍を出すほどの名書です。
失敗の科学(マシュー・サイド)
失敗から学ぶ重要性や、失敗が成長の糧となるマインドセットを科学的に解説。失敗を恐れず改善に繋げるための実践的な視点が得られます。
マインドセット:「やればできる!」の研究(キャロル・S・ドゥエック 著)
「成長マインドセット」を身につけ、失敗を学びに変える心の強さを養う名著。挑戦に対するポジティブな心構えが理解できます。
人生は見切り発車でうまくいく(奥田浩美 著)
完璧主義を手放し、70%完成で見切り発車。行動しながら改善していくスピード仕事術を実例を交えて紹介し、挑戦する勇気をくれる一冊です。
—
このブログではテレワークやパソコンを使って自宅で仕事をするために役立つ小ネタを多数紹介しています。Twitterでも情報発信していますので、今回の記事が役立ったよ!と思ったらTwitterでいいね&フォローお願いします!
Twitter: @tele_commuter