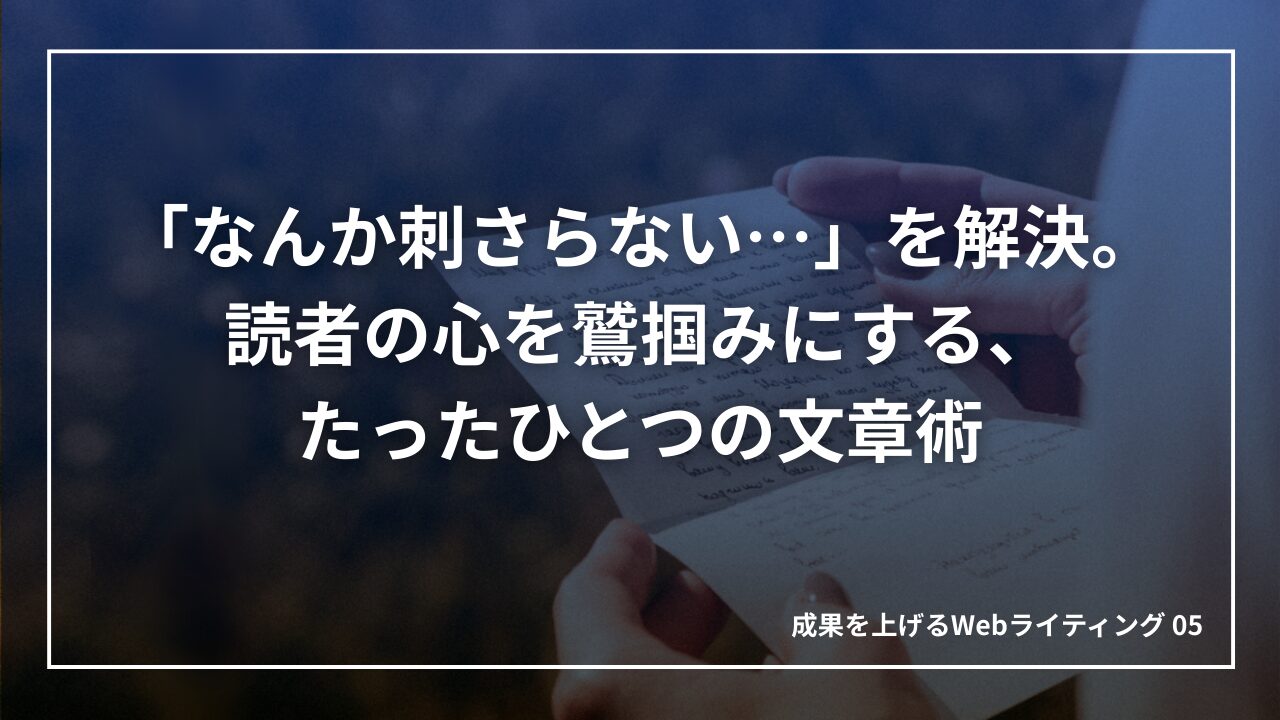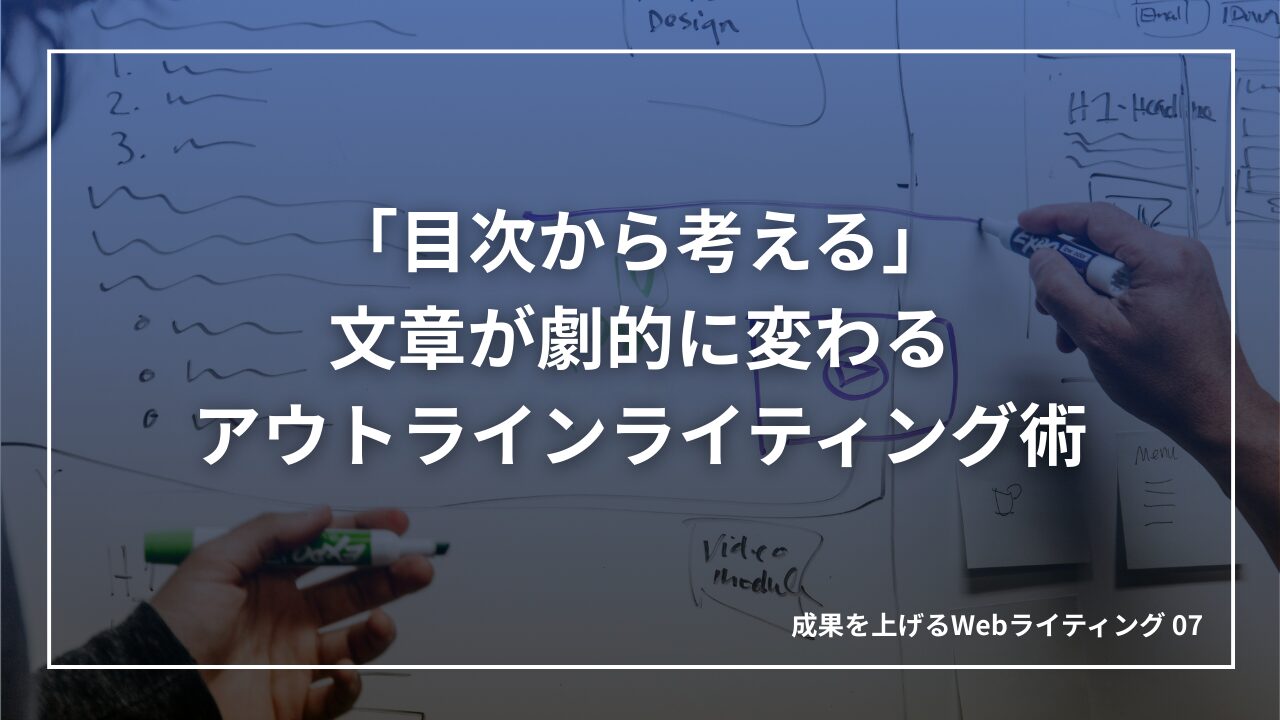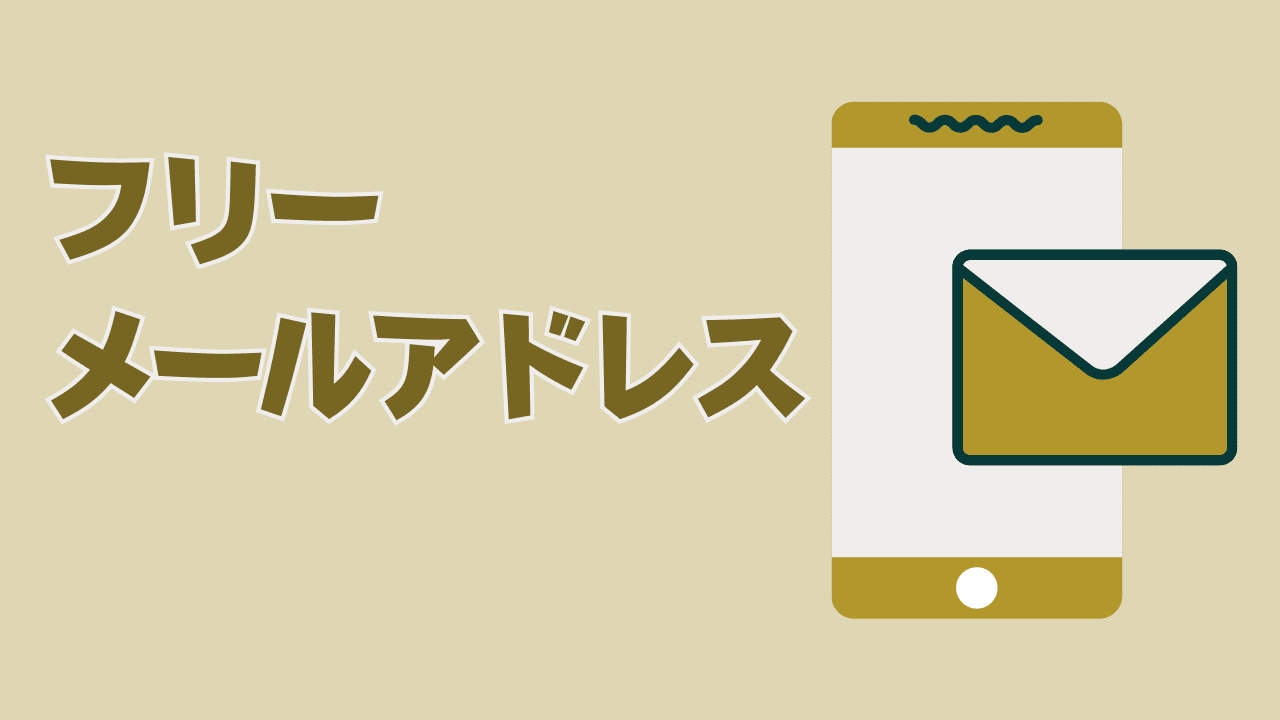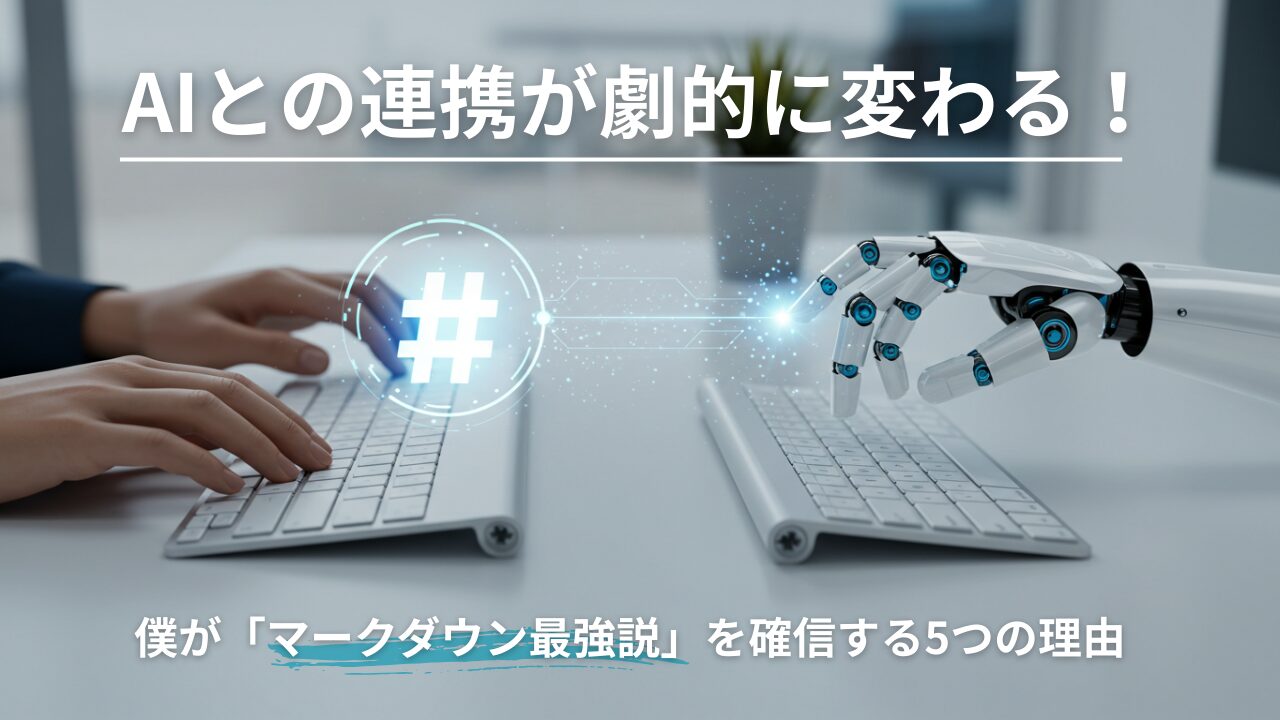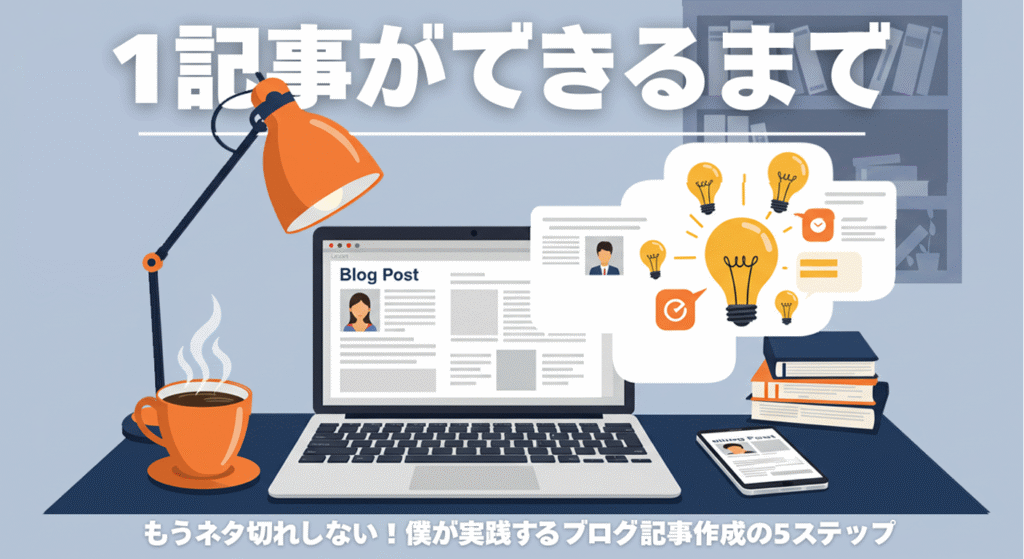
「ブログ記事って、みんなどうやって書いてるんだろう?」
「ネタ探しから公開まで、具体的な手順が知りたい…」
そんな風に思ったこと、ありませんか? 僕もブログを始めた頃、他の人の作業風景がめちゃくちゃ気になって、色々な記事を読み漁っていました。
というのも、自分のブログなんだから好きに書けばいいじゃんと思うのですが、SEO効果とか収益化とかを考えたりすると、どうやったら効率よく書けるのか?などという疑問が出てきてしまうんですよ。
そんなわけで、以前はガチガチのSEOライティングに縛られて、キーワード選定、競合分析、検索意図の深掘り…と、まるでパズルのような作業に疲弊していた時期がありました。「書くのが楽しい」なんて気持ち、どっかに行っちゃってたんですよね。
でも、ある時から「もっと自分らしく、僕と同じ感性の人に届けたい」と思うようになって、今のスタイルに落ち着きました。結論から言うと、「自分流パターン」を見つけることが、楽しく書き続ける何よりの秘訣なんです。
すると、なぜかSEO効果も上がって、収益化も以前より上回ってくるという不思議な現象が。
この記事では、僕が普段やっているブログ記事作成の全工程を、裏側まで全部お見せします!
この記事でわかること
- ネタ切れ知らずになる「ネタの仕入れ方」
- AIと協業してオリジナリティを出すアウトライン作成術
- 僕がSEOをガチガチに意識しなくなった理由
- 記事執筆のハードルを爆下げする具体的なステップ
あわせて読みたい
読者が「この記事、私のために書かれたみたい」と感じる文章の書き方とは?具体的なペルソナ設定の方法から、共感を呼ぶ語りかけのコツまで、Webライティングの質を劇的に向上させる秘訣を紹介。
STEP1:ネタの仕入れ 〜日常の「おっ?」を見逃さない〜

記事作成の第一歩は、なんといっても「何を書くか」を決めること。僕の場合、日常のあらゆる場所にネタの種が転がっていると考えています。
僕がやっている具体的なネタの仕入れ方
- Googleディスカバリーやニュースアプリを眺める:
スマホで何気なくニュースを見ている時、「おっ?」と心に引っかかるタイトルやテーマがあったら、すかさずメモします。自分が興味を持ったということは、そこには読者のニーズが隠れている可能性が高いんですよね。 - 「なぜ気になったのか?」を考える:
これ、マジで重要です。ただメモするだけじゃなく、「なんで僕はこのニュースに惹かれたんだろう?」と一歩踏み込んで考えます。タイトルが秀逸だったのか、テーマが斬新だったのか、それとも自分の悩みに直結していたのか。この「読者としての自分」を分析することが、後々の記事の方向性を決める羅針盤になるんです。 - メモは「ひとりDiscord」か「Google Keep」へ:
思いついた瞬間に、一番早く起動できるアプリに投げ込みます。スピード重視。そういう意味で最近はDiscordが多いかな。後で整理するので、この段階ではざっくりしたメモでOKです。 - Notionで一元管理:
週末などに時間を見つけて、散らばったメモをすべてNotionのデータベースに集約します。この時、「なぜ気になったのか?」の分析結果も一緒にメモしておくと、後でネタを選ぶ時にめちゃくちゃ役立ちます。
まっさらな状態から「さあ、何を書こう?」と考えても、だいたい平凡なアイデアしか浮かばないじゃないですか? でも、この方法なら、常に「自分が読者として興味を持ったこと」のストックがあるので、ネタ切れとは無縁になります。
そしてここで一番重要視しているのは、「なぜ気になったか?」の深掘りですね。僕の場合はここに一番時間をかけてるかな。
STEP2:テーマの深掘り 〜その道の「プチ専門家」になる〜

書くネタを決めたら、次はそのテーマについて徹底的に情報を集めるフェーズです。ここでの目標は、そのテーマのプロになるつもりで、誰よりも詳しくなること。というか、詳しくなろうとすること。かな。
僕は、とにかくネットで検索しまくります。関連キーワードを次々に入れて、個人ブログから公式サイト、論文まで、ありとあらゆる情報を読み漁ります。あとはBOOKOFFに行って関連書籍を大人買いしてきたりします。
これをやってると、自分自身の知識も増えるし、楽しくなるんですよね。
「え、キーワード調査はしないの?」って思いました?
正直に言うと、今の僕はホントに軽くしかやりません。 もちろん、検索ボリュームが大きいキーワードを狙うのがSEOの定石なのはわかっています。でも、それを意識しすぎると、どうしても記事が窮屈になっちゃうんですよ。
もちろん、SEOガチ勢の記事に比べたら「つよつよ記事」じゃないかもしれないけれど、それで僕自身が疲弊してしまうなら本末転倒で意味がない。実際それで1年8か月も記事を書くことから離れた時もありましたし。
キーワードに最適化された、どこかで読んだことあるような記事じゃなくて、「僕の言葉」で、「僕の体験」を届けたい。だから、検索はあくまで知識を深め、自分の考えを補強するために行います。読者が知りたいであろう情報の「解像度」を極限まで高める作業、それが大切かなと思うし、僕にとっての深掘りです。
STEP3:アウトライン作成 〜AIは優秀な壁打ち相手〜

情報収集が終わったら、記事の設計図であるアウトラインを作成します。ここが記事のクオリティを左右する、一番重要な工程かもしれません。
ちょっと前までは、集めた情報を元にうんうん唸りながら自力で構成を考えていました。でも今は、AIに相談しながら作るのが基本スタイルです。
具体的には、こんな感じでAIに話しかけます。
「〇〇(テーマ)についてのブログ記事を書きたい。読者は△△なことで悩んでいる。僕が伝えたいのは□□という視点。この情報を基に、読者が満足するようなアウトラインを提案してくれない?」
すると、AIが基本的な構成案をいくつか提示してくれます。いやぁ、これが本当に優秀なんですよ。自分では思いつかなかった切り口や、読者の潜在的な疑問点を洗い出してくれたりします。
ただし、AIの提案を鵜呑みにするのは絶対にNG ですよ。
AIの提案は、ハルシネーションがあったりするし、あくまで「叩き台」です。そこに、STEP2で深掘りした自分だけの知識や体験談、独自の視点を盛り込んで、アウトラインを再構築していきます。
- この章とこの章は入れ替えた方が自然だな…
- AIの提案にはないけど、僕の失敗談は絶対に入れたい!
- この部分は、もっと僕の言葉で熱く語るべきだ。
それで文章がうまく繋がらなくなったら、そこでまたAIに相談ですよ。「ここのところがうまく繋がらないんだよ。どうすればうまくまとまるかな?」って。
この「AIとの共同作業」こそが、効率化とオリジナリティを両立させる鍵だと思いませんか? AIという優秀な壁打ち相手がいることで、思考が整理され、記事の骨格がより強固なものになっていくんです。
そして、自分だけの知識や体験談、独自の視点を盛り込んでいく。これがコンテンツとしてとっても重要だと思います。
イメージとしては、隣の席の同僚に「これどう?もっといい案ある?」と話しかけながら仕事をしているという感じですね。全部AIに投げて自動化するのも面白いけど、やっぱりそこは自分で書く楽しさが記事の熱量となって表れると思うので、僕にとってAIは自動化ツールじゃなくて相談相手ですよね。
「書きたいのに書けない…」その悩み、もくじ(構成)で解決できます。本記事では、執筆スピードと質を劇的に上げる「もくじファースト」思考法を徹底解説。もう文章で迷子にならない、論理的な記事構成の作り方がわかります。
STEP4:肉付け 〜魂を吹き込むライティング〜

しっかりしたアウトラインさえ出来てしまえば、記事のメインである肉付け作業は驚くほど楽になります。各見出しが「何を書くべきか」を明確に示してくれているので、あとはそれに従って自分の言葉を紡いでいくだけ。
僕がこのフェーズで意識しているのは、とにかく読者に語りかけること です。
一方的に情報を伝えるのではなく、「~ですよね?」「僕もそうだったんですよ」と、常に読者との対話を意識します。難しい言葉は使わず、友人に「ねぇ、聞いてよ!」と話しかけるような熱量で書く。
完璧な文章を目指す必要はありません。それよりも、あなたの感情や体験が乗った、熱のある言葉の方がずっと読者の心に響くはずです。
もし筆が止まったら、それはアウトラインが曖昧な証拠かもしれません。そんな時は一度STEP3に戻って、アウトラインをさらに具体的にしてみることをお勧めします。
読者が「この記事、私のために書かれたみたい」と感じる文章の書き方とは?具体的なペルソナ設定の方法から、共感を呼ぶ語りかけのコツまで、Webライティングの質を劇的に向上させる秘訣を紹介。
STEP5:画像の用意 〜Canvaと生成AIは神〜

文章が完成したら、最後に記事を彩る画像を用意します。文章だけの記事は、どうしても読者が疲れてしまいますからね。
以前はフリー素材サイトを延々と探し回っていましたが(これが一番時間がかかっていた…!)、今はもうCanva一択と言っても過言ではありません。
Canvaの何がすごいって、テンプレートがおしゃれなのはもちろん、テキストを入れたり、図形を組み合わせたりするのが直感的にできるところ。アイキャッチ画像や図解の作成が、本当にすぐ終わります。
以前は講師をしていたのもあって、Photoshopで何でも作っていましたけど、ブログのアイキャッチや挿絵だったら、もうCanvaでやる方が早いしラクラク。
さらに、人物のイメージ画像が欲しい時は、生成AIを使うのもめちゃくちゃアリです。MidjourneyやStable Diffusionのような画像生成AIを使えば、記事の雰囲気に合ったオリジナルの人物画像を簡単に作り出せます。
無料だったらImageFXやImagenやNano Bananaとか使いやすいと思います。僕はよく使います。この記事の画像はすべてAIで生成した画像ですし、この上の女性の画像もAIで作成した画像です。めちゃくちゃクオリティ高いですよね。「草原で振り向く日本人女性」というプロンプトでここまでリアルな画像が生成できます。
もう、「イメージに合う素材が見つからない…」と時間を溶かす必要はないんです。便利なツールを使い倒して、効率的に、かつクオリティの高いビジュアルを用意しましょう。
こちらに、Canva関連の記事をまとめてあります。
まとめ:あなただけの「自分流パターン」を見つけよう
今回は、僕がブログ記事を1本書き上げるまでの全工程を、包み隠さずお話ししました。
僕流・記事作成の5ステップ
- ネタの仕入れ: 日常の「おっ?」をメモし、Notionにストックする。
- テーマの深掘り: プロになるつもりで情報を集め、解像度を上げる。
- アウトライン作成: AIと壁打ちしながら、オリジナルの設計図を作る。
- 肉付け: 読者との対話を意識し、熱量を持って書き上げる。
- 画像の用意: Canvaと生成AIを使いこなし、効率的にビジュアルを作る。
たぶん、一般的なSEOライティングのセオリーとは違う部分も多かったかもしれません。キーワードツールとか一回も出てきませんでしたしね。でも、大事なのは 「自分がいかに楽しく、継続して発信できるか」だと僕は思っています。
それにしてもこうして振り返ると、僕の記事の生命線はメモアプリだなぁと思いました。中でも「ひとりDiscord」「Google Keep」「Noiton」は絶対外せないし、「Microsoft To Do」もリマインダーとして外せない。いつか、これらのメモアプリ紹介記事も書いていこうと思います。
この記事で紹介した僕のやり方が、あなたにとっての「正解」とは限りません。でももし、「ブログのネタがない」「書くのが辛い」と思っていたり、SEO重視のライティングに疲れているのなら、この中から「これなら真似できそう」と思った部分だけでも、つまみ食いして「自分流パターン」を見つけてみてください。そしてまたブログ仲間として楽しい時間を過ごしましょう!
おすすめの書籍

この記事に関連するブログ運営・ライティングスキル向上に役立つ書籍をご紹介します。今回の記事内容に関連する実用的な本を中心に選定しました。
ブログライティング・文章術
『文章力の基本』
「読者との対話を意識した文章」を書くための基本的な技術が学べます。特に分かりやすい表現や読み手を意識した構成について詳しく解説されています。
『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』
「自分らしい文章」を書くためのヒントが100冊分凝縮されています。AIに頼らない独自性のある文章術が身につきます。
『新しい文章力の教室』
記事のアウトライン作成から肉付けまでの具体的な手順が詳しく書かれており、情報の整理や論理的構成を読者目線で実践できるメソッドが学べます。それに、読みやすい文章・伝わる文章作りを理論と実践両方から鍛えることができます。
ブログ運営・コンテンツ戦略
『ブログ飯』
SEOに縛られすぎず、読者に価値を提供することでブログを収益化する方法が書かれています。「自分らしく書く」スタンスの方向性が好きです。
『ゼロから学べるブログ運営×集客×マネタイズ』
ネタ探しから記事作成、継続的な運営まで、ブログの全工程を体系的に学べます。特にコンテンツの企画・制作部分が参考になるでしょう。
『ブログで5億円稼いだ方法』
初の著書とは思えないほど読みやすいし理解しやすく書かれた良書。ブログ運営に関して長い実績があるだけに、そのノウハウには重みがあります。とてもまじめな本だと思います。
SEO・Webマーケティング
『沈黙のWebライティング』
SEOを意識しつつも読み手本位のコンテンツ作りを学べる名著です。何度も繰り返し読みました。SEOの松尾さんの書籍ですが「SEOガチガチではない」アプローチのバランス感覚が身につきます。コンテンツの本質を学べます。
『10年つかえるSEOの基本』
小手先のテクニックではなく、本質的なSEOの考え方が学べます。キーワード選定に頼らないコンテンツ作りの参考になります。
アイデア発想・情報収集
『アイデアのちから』
日常の「おっ?」を記事ネタに変換する力を高めるのに最適です。記憶に残るアイデアの特徴や、情報を魅力的に伝える方法が学べます。
『考具』
2003年の本なんですね。めちゃくちゃ売れましたよね。ネタ探しや企画立案のための具体的な手法が21個紹介されています。あなたのメモ術をさらに発展させるヒントが見つかるでしょう。
—–
このブログではテレワークやパソコンを使って自宅で仕事をするために役立つ小ネタを多数紹介しています。Twitterでも情報発信していますので、今回の記事が役立ったよ!と思ったらTwitterでいいね&フォローお願いします!
Twitter: @tele_commuter